2023.08.02
武田信玄|どぼく偉人ファイルNo.11 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第11回は信玄堤(しんげんづつみ)などの治水事業を推進した戦国時代の武将、武田信玄です。
文:三上 美絵(ライター)
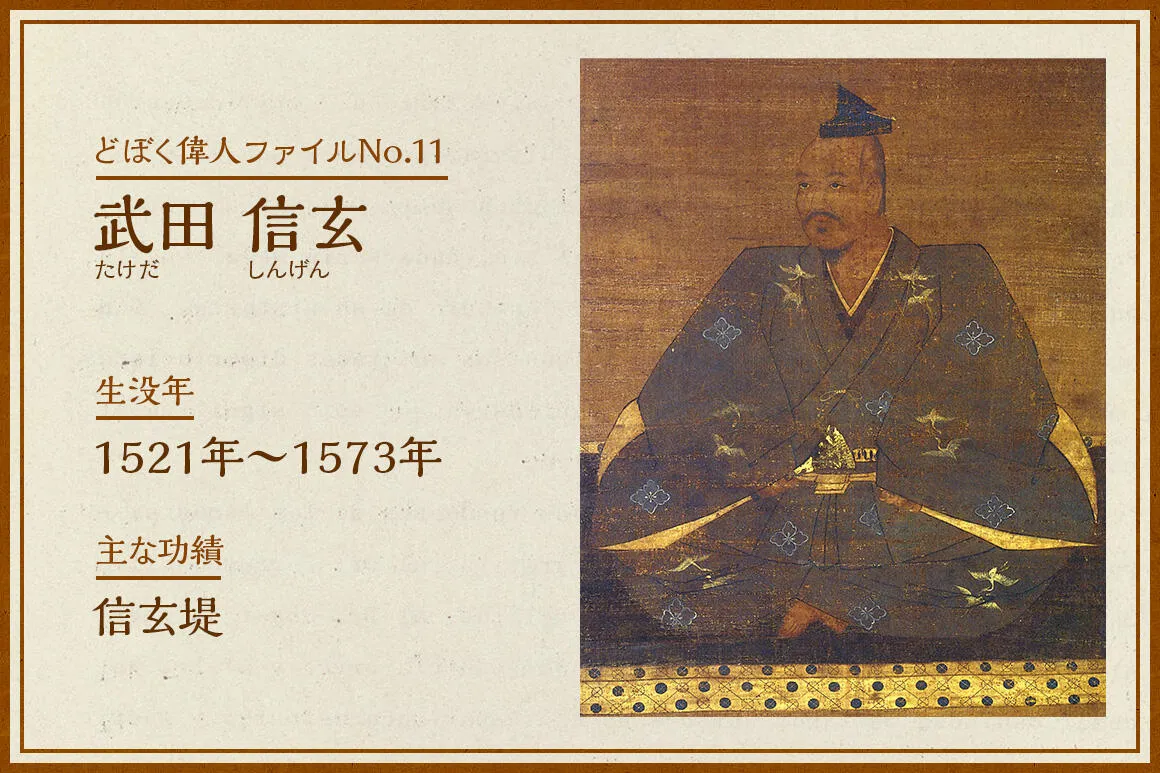
Before:長い間、洪水を繰り返してきた甲府盆地
山梨県の甲府盆地は、富士川の上流である釜無川(かまなしがわ)などによってつくられた扇状地だ。扇の要にあたる扇頂部は「竜王の鼻」と呼ばれ、そのすぐ上流で、支川である御勅使川(みだいがわ)と合流している。
2つの川がたびたび流路を変えながら扇状地を流れていたため、この地域は古くから大雨のたびに洪水や氾濫が絶えず、人々は家や田畑が浸水する危険と常に隣り合わせだった。
 現在の甲府盆地の様子。水色の部分が氾濫域(出典:国土交通省甲府河川国道事務所パンフレット「歴史に学ぶ治水の智恵 富士川の治水を見る 」を加工して作成、提供:株式会社サンニチ印刷)
現在の甲府盆地の様子。水色の部分が氾濫域(出典:国土交通省甲府河川国道事務所パンフレット「歴史に学ぶ治水の智恵 富士川の治水を見る 」を加工して作成、提供:株式会社サンニチ印刷)
After:20年越しの大治水事業で暮らしが安定
武田信玄が甲斐国主となった翌年の1542年、御勅使川の大氾濫が一帯を襲った。これをきっかけに、信玄は大規模な治水事業を計画。「石積み出し」(石積みの堤防)によって御勅使川の流れを整え、「将棋頭(しょうぎがしら)」(将棋の駒のような形の水制)で2つに分けて勢いを弱める。合流した御勅使川と釜無川の流れを自然の崖である「高岩(たかいわ)」に当て、後に「信玄堤」と呼ばれるようになった長い堤防を築く。さらに下流には「霞堤(かすみてい)」(切れ目を入れた不連続な堤防)を設け、あふれた水が川に戻るようにした。
20年の歳月をかけて一連の治水事業を実施した結果、御勅使川と釜無川は安定し、水害が減少した。信玄堤をはじめ、信玄の時代につくられた治水システムは、現在も甲府盆地を洪水や氾濫から守っている。
 武田信玄の行った治水事業(出典:国土交通省甲府河川国道事務所パンフレット「歴史に学ぶ治水の智恵 富士川の治水を見る」を加工して作成、提供:株式会社サンニチ印刷)
武田信玄の行った治水事業(出典:国土交通省甲府河川国道事務所パンフレット「歴史に学ぶ治水の智恵 富士川の治水を見る」を加工して作成、提供:株式会社サンニチ印刷)
 (左)現在の釜無川と信玄堤(右)信玄堤の前には「聖牛(せいぎゅう・ひじりうし)」と呼ばれる水制も設置されている
(左)現在の釜無川と信玄堤(右)信玄堤の前には「聖牛(せいぎゅう・ひじりうし)」と呼ばれる水制も設置されている
(出典:国土交通省甲府河川国道事務所パンフレット「ふるさとの川を見てみよう!!」、提供:株式会社サンニチ印刷)
武田信玄のここがスゴイ! 〜ミカミ'sポイント〜
Point1:自然を生かした甲州流の治水技術を確立
戦国武将たちにとって、洪水対策は最重要課題だった。国力を高めなければ他国との戦には勝てず、国力を高めるには経済力が必要で、経済力は労働人口と農業生産に支えられていたからだ。田畑を拓き、人々の暮らしを安定させるには、まず水害をなくさなければならない。
領主となった信玄は、釜無川と御勅使川周辺の地形や水の流れを調べ、家臣たちとの合議によって、段階的に水流を弱める方法を編み出した。自然の地形を利用し、流れに逆らわずに洪水被害を減らすこうした治水技術は、江戸時代に「甲州流」と呼ばれ、いくつかある川除(かわよけ、治水法のこと)の中で最も重視されるものになった。
Point2:「お祭り」で治水の重要性をアピール
これほど大規模な治水事業を成し遂げたプロジェクト推進力もさることながら、もう1つ信玄がスゴイのは、さらに先を見越して持続的な維持管理システムをつくったことだ。
そのシステムとは、信玄堤沿いに「竜王河原宿(りゅうおうかわらじゅく)」を設けて移住者を募集し、新田の開発と、日常的な堤防の補修や水害時の防備に当たらせるもの。家ごとにかかる租税を免除する特典を付けたこともあって、河原宿には50軒が移り住んだという。
また、信玄は平安時代から伝わる水防のお祭りである「御幸祭(みゆきまつり)」を奨励し、盛大に行った。「おみゆきさん」と呼ばれるこの祭りでは、笛吹市にある浅間神社(あさまじんじゃ)から竜王河原宿の三社神社まで、神輿(みこし)を担いで練り歩く。大勢の足で堤防を踏み固めるとともに、治水の大切さを民衆に伝えるための広報活動の意味もあった。
※記事の情報は2023年8月2日時点のものです。

- 三上美絵(みかみ・みえ)
土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。






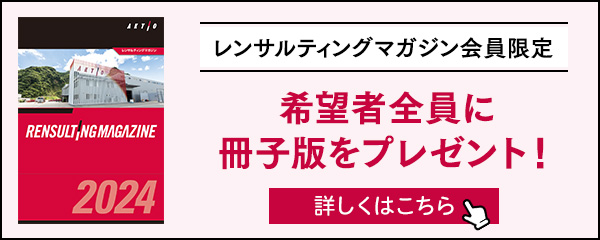













![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

