2022.10.05
後藤新平|どぼく偉人ファイルNo.07 土木大好きライター三上美絵さんによる「どぼく偉人ファイル」では、過去において、現在の土木技術へとつながるような偉業や革新をもたらした古今東西のどぼく偉人たちをピックアップ。どぼく偉人の成し遂げた偉業をビフォーアフター形式でご紹介します。第7回は関東大震災後の帝都復興事業に尽力した後藤新平です。
文:三上 美絵(ライター)
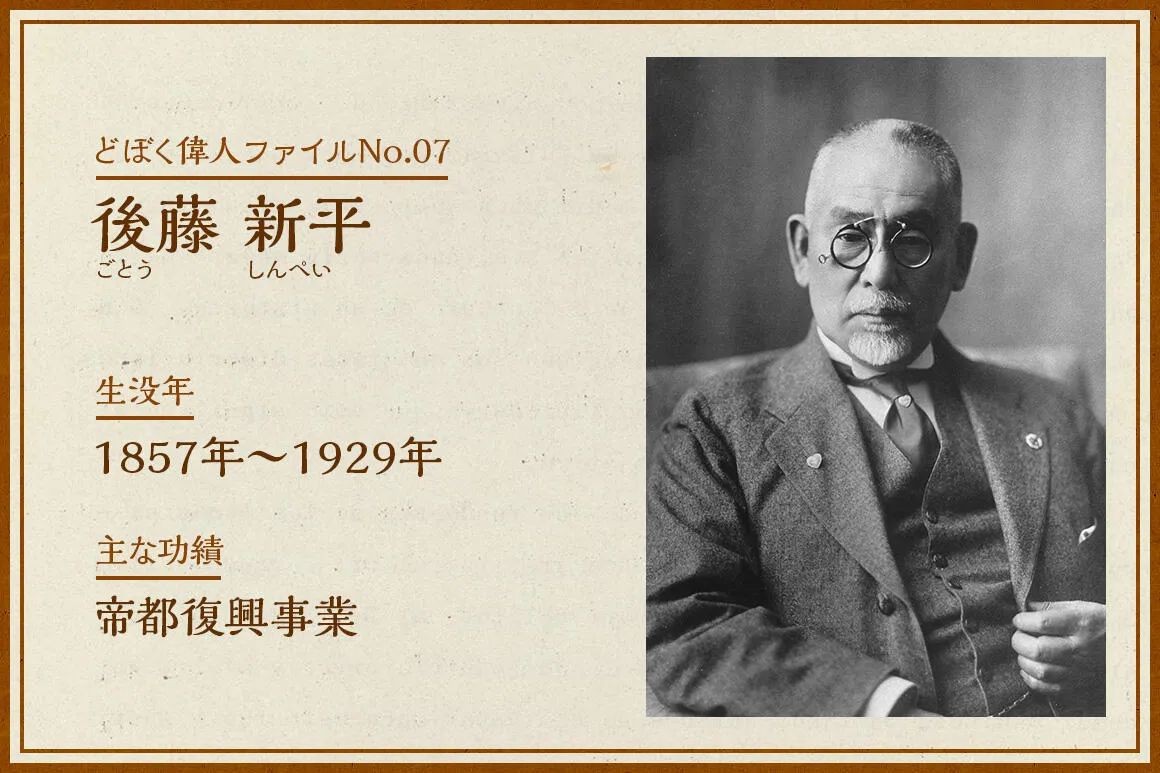
Before:関東大震災で帝都・東京に壊滅的な被害
1923(大正12)年9月1日の午前11時58分、関東大震災が発生した。神奈川県西部を震源とするマグニチュード7.9の大地震だ。死者・行方不明者は10万5000人を超え、そのうちの9割近くが火災による犠牲者だった。
昼どきで多くの家に火の気があり、家屋の倒壊が多かった下町一帯では地震直後から火災が広まった。東京では3日の朝まで火は消えず、家屋の倒壊が少なかった地域まで延焼。現在の東京23区に相当する東京市域の44%の面積が焼失した。
震災翌日の9月2日、内務大臣に就任したのが後藤新平だ。後藤の提案により、被災した東京と横浜の復興計画の策定・執行を担う「帝都復興院」と、計画の審議を担う「帝都復興審議会」が設立された。後藤は自ら帝都復興院の総裁を兼務し、優秀な技術者を集めて復興計画を練り上げた。
後藤の率いる帝都復興院が立てた当初計画では、理想案の事業費が概算41億円に上ったが、財政事情を考慮し、約13億円の政府原案とした。しかしこの案も、大蔵省との折衝や審議会の審議を受けてさらに大幅に修正され、最終的に国会において約5億7000万円で可決された。
 東京の日本橋から神田方面の関東大震災の被災状況(出典:大阪毎日新聞社 - 関東震災画報)
東京の日本橋から神田方面の関東大震災の被災状況(出典:大阪毎日新聞社 - 関東震災画報)
After:現在へ続く首都・東京の基盤ができた
復興事業の執行は、内務省復興局が帝都復興院の計画を引き継いで担うことになった。事業の中心となったのは、区画整理と幹線道路整備、公園整備、橋梁や公共施設などの建設だ。
区画整理では、「計画地の地権者は土地の1割を無償で提供する」という案に対して猛烈な反対運動が起こったものの、後藤らが講演会など啓蒙活動を行った結果、数カ月で終息。江戸から続く密集市街地やあぜ道のまま宅地となった下町地域は、3,600haにわたる区画整理によって、生活道路網や上下水道、ガスなどが整備された近代的な街並みとなった。
東京の幹線道路整備は52路線に及び、今も都内の主要な通りとなっている。南北に昭和通りができ、東西の大正通り(靖国通り)は拡幅。東京駅を中心とした放射道路と環状道路の組み合わせもこの時に原型ができた。
公園整備では、「東京の震災復興三大公園」と呼ばれる隅田公園、浜町公園、錦糸公園を新設。木造だった学校は鉄筋コンクリート造へ、橋梁は鉄製へと生まれ変わった。
区画整理や幅の広い幹線道路、広い緑地公園で火災時の延焼を食い止め、建物や構造物は燃えにくいコンクリートと鉄に変える。後藤の構想は当初に比べて縮小されたとはいえ、その思想は受け継がれ、災害に強く憩いのある現代の首都・東京の基盤につながったのである。
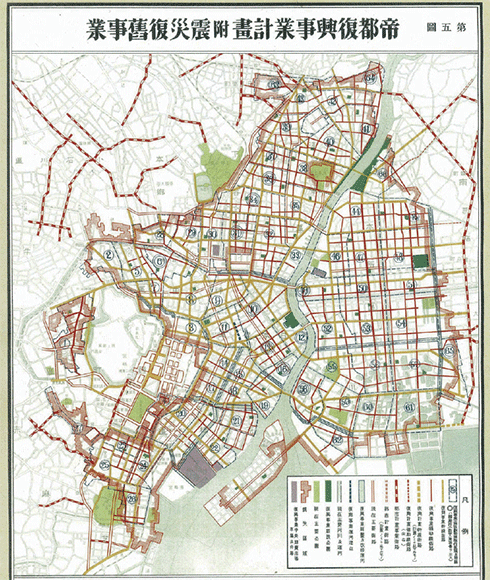 帝都復興計画事業図(出典:東京市「帝都復興事業図表」1930(昭和5)年3月)
帝都復興計画事業図(出典:東京市「帝都復興事業図表」1930(昭和5)年3月)
 震災復興三大公園の一つ、隅田公園の1931(昭和6)年当時の様子(土木図書館所蔵)
震災復興三大公園の一つ、隅田公園の1931(昭和6)年当時の様子(土木図書館所蔵)
 隅田川に架かる復興橋梁の一つ、現在の清洲橋
隅田川に架かる復興橋梁の一つ、現在の清洲橋
後藤新平のここがスゴイ! ~ミカミ'sポイント~
Point1:「自治の精神」を理念に掲げた都市計画家
後藤は、旧来の東京をそのままの形で再建することは考えず、震災を「理想的帝都建設のための絶好の機会」と位置づけ、抜本的な都市改造による首都復興を目指した。
震災前には東京市長を務め、街路や公園の新設、下水の改良、田園都市の建設などからなる東京改造論を「東京市政要綱」として発表。市の年間予算が1億3000万円だった時代に、8億円近くかかる計画をぶち上げ、「後藤の大風呂敷」と揶揄(やゆ)された。だが、この「8億円計画」という土台があったからこそ、震災後の短期間で復興計画をまとめ上げることができたのだ。
「自治は市民一人ひとりが市長である」「都市計画は自治の精神を離れてはいけない」という信念のもと、震災後の復興では市民の痛みを伴う区画整理を断行。現代でも通用する都市運営の理念を掲げた後藤は、復興事業が完了する前年の1929年に脳溢血(のういっけつ)のため世を去った。
Point2:「おさな心」を忘れない魅力的リーダー
医師であり、政治家であり、都市計画家でもあった後藤には、ボーイスカウト日本連盟の初代会長という別の顔もあった。「政治家はしかつめらしいことばかり言っていてはだめだ。稚気がないといかん」と語り、半ズボンの制服姿で全国を巡回。あえてそのままの服装で役所へ出勤したこともあったという。スカウトの子どもたちからも慕われていた。
帝都復興院に集められたメンバーの中には、後藤の"腹心"と呼ばれた人物も多く、復興院が廃止された際に「後藤さん以外の下で働く気はない」と言って去る者もいた。
若い都市計画家を前にした講演会では、自ら手がけてきた都市計画の成功と失敗を率直に語り、次世代の糧(かて)とした。奇しくも脳溢血で倒れる直前に語った「金を遺して死ぬ者は下だ。仕事を遺して死ぬ者は中だ。人を遺して死ぬ者は上だ」という言葉に、後藤の人材育成への思いが溢れている。
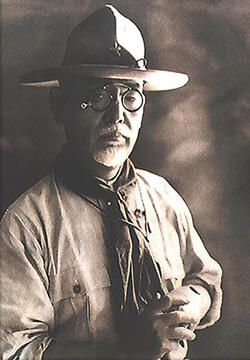 ボーイスカウトの制服姿の後藤新平(出典:Wikipedia)
ボーイスカウトの制服姿の後藤新平(出典:Wikipedia)
※記事の情報は2022年10月5日時点のものです。
-

- 三上美絵(みかみ・みえ)
土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。




















![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

