2022.11.30
【建設×SDGs➄】鉄鋼業のカーボンニュートラル〈前編〉水素を活用して製造プロセスでのCO2を削減 日本をはじめ先進国は、「2050年までに温室効果ガスをゼロにする」目標を掲げています。温室効果ガスの多くを占めるのが二酸化炭素(CO2)で、そのCO2排出量を全体としてゼロにするのが「カーボンニュートラル」。鉄鋼業は国内CO2排出量の約14%(電力配分後)を占め、産業部門の中では40%を占め最も多いのが現状です。鉄鋼業がどんな方法でCO2削減にチャレンジし、鉄鋼を多く利用する建設業界にはどのような影響があるのか。前後編にわたって、一般社団法人日本鉄鋼連盟(以下、鉄鋼連盟)に聞きました。前編ではCO2削減プロジェクトについて、「カーボンニュートラルスチール推進タスクフォース座長」を務める礒原豊司雄(いそはら・としお)氏にうかがいます。
文:長坂 邦宏(フリーランスライター) 写真:安達 康介

「3つのエコ」を推進
――カーボンニュートラルへの具体的な取り組みは、鉄鋼連盟としていつ頃から始めたのでしょうか。
2013年に日本経済団体連合会(経団連)の「低炭素社会実行計画(現:カーボンニュートラル行動計画)」が始まったことを受けて、鉄鋼連盟は同計画を推進し、「3つのエコ」と「革新的技術開発」によるエネルギー起源CO2の排出を削減するための自主的な取り組みを始めました。3つのエコとは、自らのプロセスにおけるCO2排出削減取り組みを行う「エコプロセス」、製品の使用段階でのCO2排出削減に貢献する「エコプロダクト」、そして日本鉄鋼業が実装している優れた省エネ技術をグローバルに展開して、世界のCO2排出削減に貢献する「エコソリューション」です。

2015年12月に地球温暖化防止のための国際枠組みである「パリ協定」が締結され、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標が掲げられました。このため、鉄鋼連盟は2030年以降を見据え、最終的なCO2排出実質ゼロを目指した「長期温暖化対策ビジョン-ゼロカーボン・スチールへの挑戦-」を2018年11月に策定しました。このビジョンで は1.5℃シナリオへの超革新技術の必要性を示しています。
その後、菅内閣総理大臣(当時)から2050年カーボンニュートラル宣言が行われたことを踏まえ、鉄鋼連盟では、2021年2月に「我が国の2050年カーボンニュートラルに関する日本鉄鋼業の基本方針」を策定し、我が国の2050年カーボンニュートラルという野心的な方針に賛同し、これに貢献すべく、日本鉄鋼業としてもカーボンニュートラルの実現に向けて、果敢に挑戦することを表明しています。
──具体的なCO2削減プロジェクトを理解するために、まずは鉄を作る仕組みを簡単に教えていただけますか。
原料は酸化鉄を主成分とする鉄鉱石を使います。鉄鉱石中の酸化鉄から酸素を取り除くために、より酸素と結び付きやすいコークス(石炭を乾留して固形の炭素分にしたもの)と高温で反応させると、酸化鉄から酸素を奪い取り、溶けた鉄が取り出せます。これを還元反応といい、この還元処理を行うための設備を高炉と呼びます。高炉は効率的かつ大規模な鉄鋼生産を可能にする優れた設備である一方、この反応からは大量のCO2が発生し、その割合は鉄鋼製造プロセス全体の7〜8割にもなるといわれています。
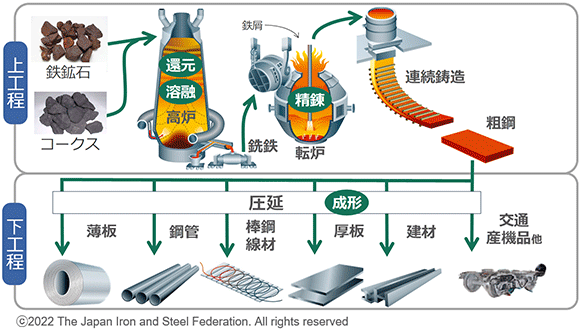 鉄鋼製造プロセスの概要と製造される主な製品(出典:日本製鉄)
鉄鋼製造プロセスの概要と製造される主な製品(出典:日本製鉄)
コークスの一部を水素に代替
──CO2削減のために、現在どんなプロジェクトに取り組まれていますか。
日本の鉄鋼業は長年にわたり世界最高水準の省エネ技術実装に力を入れており、すでにそれら省エネ技術によるCO2排出削減余地はほとんどありません。既存の省エネ技術ではCO2排出をこれ以上大幅に減らすことはできないので、高炉での還元反応段階で発生するCO2排出を削減するしかありません。そこで国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と鉄鋼メーカーは「COURSE50」と呼ぶプロジェクト※を実施し、研究開発を進めています。また、COURSE50の技術を生かし、さらにCO2排出を削減する「Super COURSE50」についても取り組みを進めています。
それらのプロジェクトでは、還元材であるコークスの一部を水素に代替して鉄鉱石を還元するとともに、高炉排出ガスからCO2を分離・回収します。水素を還元材に使った場合、CO2は発生しないので、コークスを減らした分だけCO2排出を削減することができます。COURSE50では、還元材の一部を水素に置き換えることで高炉からのCO2排出量を10%削減し、CO2の分離・回収でCO2排出量を20%削減するのが目標であり、Super COURSE50では水素の投入割合をさらに高めることを目指しています。
なぜ還元材を水素へ置き換えることでの削減分が10%かというと、水素が大量に入手することが困難な現状において、コークス炉でコークスを作る時に発生するガスから水素を回収すれば、10%削減相当の水素であれば製鉄所内で水素を賄えるからです。2016年度から試験高炉を用いた研究開発が行われており、2030年頃の実用化を目指しています。
※プロジェクトの正式名称は、「環境調和型プロセス技術の開発/水素還元等プロセス技術の開発(フェーズII-STEP1)」。
 NEDOと鉄鋼各社が共同研究で使用する試験高炉(出典:NEDO・日本鉄鋼連盟 COURSE50)
NEDOと鉄鋼各社が共同研究で使用する試験高炉(出典:NEDO・日本鉄鋼連盟 COURSE50)
──Super COURSE50についても教えてください。
1.5℃シナリオが出た後、我が国を含めて世界各国で2050年カーボンニュートラルを目標とすることが宣言され、より野心的な低炭素化に向けた取り組みが必要となっています。一方、高炉にもっと水素を投入してCO2排出量を減らそうとしても、現状、製鉄所内で発生する水素ではその供給が足りません。他方、国では2050年に2,000万t程度の水素導入量を目指していることから、鉄鋼製造プロセスでもそれら外部水素を活用した取り組みが期待できるため、既存高炉法をベースに可能な限り、水素を還元材として用いる方法の開発に挑戦することとなりました。それがSuper COURSE50です。
ただ、課題もあります。高炉は内部でコークスの層と鉄鉱石の層を交互に入れて層状に積み重ねています。下から熱風を吹き込み、コークスを加熱して鉄鉱石を還元し、コークスの隙間から溶けた鉄が高炉の下部に溜まる仕組みになっています。コークスは1,500℃ほどの高温でガス化し体積を減らしていきますが、最後まで固体のままで、高炉内部の装入物を支えています。しかし水素をたくさん入れると、このコークスの量が減り、層状になったコークスと鉄鉱石を支えきれなくなってしまうのです。ここに高炉法の原理的な限界があります。
ですので、Super COURSE50で水素を何%まで投入できるかは、前人未到の領域と言えます。
──水素還元製鉄という方法もありますね。100%水素を使い、CO2排出ゼロを目指せるのではないでしょうか。
水素還元製鉄は、シャフト炉という高炉とは別形式の炉に鉄鉱石を投入し、炉内に水素を吹き込むことで還元反応を起こすもので、原料としてはペレットと呼ばれるビー玉のように丸めた鉄鉱石を使います。シャフト炉を用いてガスにより鉄鉱石還元を行う設備は、DRI(直接還元鉄)プラントと呼ばれ、現在でも天然ガス(炭素と水素の化合物であるメタンが主成分)を吹き込んで還元反応を行い、鉄が作られています。この方法は米国や中東諸国など天然ガスが安く手に入る国では一部利用されておりますが、天然ガスが高い日本では行われていません。
この方法なら天然ガスを水素に置き換えることにより、水素100%での還元を実現することができますが、還元された鉄は高炉のように溶けて出てくるのではなく固体の鉄で出てくるため、それを融(と)かす電気炉が別途必要になるなど、高炉ほどエネルギー効率は良くなく、大規模生産には向いていないといった課題があります。
これまで述べたような革新的技術の開発・実装には、それぞれ乗り越えるべき壁が多く存在するため、COURSE50、Super COURSE50、水素還元製鉄の研究開発を並行して複線的に進めていこうという方針を鉄鋼連盟はロードマップで示しています。
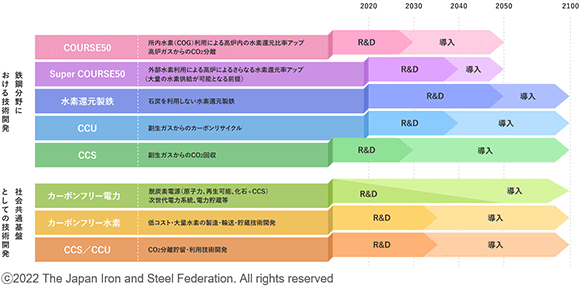 カーボンニュートラルを目指した日本鉄鋼連盟のロードマップ(出典:日本鉄鋼連盟)
カーボンニュートラルを目指した日本鉄鋼連盟のロードマップ(出典:日本鉄鋼連盟)
CCU、CCSとの併用でCO2を削減
──CO2を削減するために、ほかに取り組まれていることはありますか。
高炉を用いるCOURSE50、Super COURSE50はCO2排出量を削減できるとはいえ、CO2をゼロにすることはできません。残ったCO2はCCU(二酸化炭素の回収・有効利用)、CCS(二酸化炭素の回収・貯留)を用いて、さらに削減しようと考えています。COURSE50では、還元材の一部を水素に転換することで10%減らしますが、CCU、CCSも織り込み済みで、それらでさらに20%減らして合計30%削減する目標を掲げています。
CCU、CCSでは最初にCO2を吸収・回収する工程が必要になるため、高炉ガスからの回収に適した吸収液の開発が行われています。吸収液がCO2だけを吸収してからCO2を再分離して回収するときにはその吸収液に熱を与える必要がありますが、その際にできるだけ低い温度で処理できるようにし、処理に必要なエネルギーをなるべく減らすことがポイントです。
CCSは、枯渇した油田・ガス田や帯水層などの地中に圧入してしまう方法が検討されています。鉄鋼連盟としては吸収液の開発まで行い、CO2の貯留場所は国にお願いいするというスタンスです。
CCUでは回収したCO2はパラキシレンなどの化学品製造の原料として利用できないか研究されています。
──COURSE50、Super COURSE50プロジェクトはどのようなスケジュールで進めているのですか。
COURSE50プロジェクトは2008年から始まり、2016年3月には試験高炉が日本製鉄君津地区構内に完成しました。これまでのCOURSE50プロジェクトを通じ、試験高炉レベルでの実用性は確認しています。2030年までに少なくとも1基は商用炉を実装する計画です。
Super COURSE50も同じ試験高炉を使って研究を進めています。2020年に研究開発を始め、今のロードマップでは2040年頃に実機実証を目指しています。
──製鉄には、電炉を使う方法もあります。電炉の現状についても教えてください。
高炉は主に鉄鉱石から鉄鋼を製造する方法ですが、電炉は鉄鋼スクラップが主原料になります。鉄鋼スクラップの発生量は鉄鋼蓄積量(建築物や自動車など何らかの形で社会で使用されている鉄鋼の総量)の増加に応じて、今後確実に増えていきます。今、世界の鉄鋼生産の中でスクラップを使用している割合は鉄鋼製造量全体の30%強になっていて、2050年には半分ぐらいになるだろうと予測されています。
電炉から発生するCO2排出量は、鉄鋼の製造段階だけを見れば高炉からの排出量の約4分の1といわれており、今後、鉄鋼スクラップ発生量が増大していくこともあり、電炉による鉄鋼の製造割合が増えていくのは間違いないでしょう。ただCO2排出量を考える上で大切なことは、鉄鋼の製造段階だけでなく、使用・リサイクルを含めたライフサイクル全体で見ることです。リサイクルも含めたライフサイクル全体で見れば、高炉で作った鉄鋼も電炉で作った鉄鋼もCO2排出量は等価です。また、資源のサステナビリティーという意味でも、鉄のリサイクル性の高さはとても重要であり、地球上にある鉄鋼をうまくリサイクルしながら、活用していくことが重要と考えています。
※記事の情報は2022年11月30日時点のものです。

- 礒原豊司雄(いそはら・としお)
1961年生まれ。日本製鉄株式会社技術総括部部長代理、一般社団法人日本鉄鋼連盟技術政策委員会企画委員会座長、同カーボンニュートラルスチール推進タスクフォース座長。1987年東京大学大学院工学系研究科化学工学専攻修士課程修了。同年、新日本製鐵株式会社入社。先端技術研究所、知的財産部、技術開発企画部、環境基盤研究部等を経て現職。鉄鋼製品のLCA、サステナビリティー、低炭素化等に従事。
〈後編〉へ続く




















![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

