2022.01.05
【建設✕SDGs①】循環型社会に貢献する「次世代コンクリート」〈前編〉コンクリート瓦礫のリサイクルで環境負荷を軽減 建築物や構造物を造るときに不可欠な存在の1つがコンクリートです。しかし、現在流通しているコンクリートの多くはその製造過程で大量のCO₂を排出することから、環境負荷を軽減するための取り組みが欠かせません。東京大学生産技術研究所の酒井雄也(さかい・ゆうや)准教授は、さまざまな角度からコンクリートを研究し、環境に優しい建築材料の開発に力を注いでいます。酒井准教授に環境に配慮した「次世代コンクリート」について、お話をうかがいました。
写真:安達 康介

粉体を固めて強いコンクリートに再生
――まずは、先生がコンクリートに関わるようになったきっかけについて教えてください。
高専(高等専門学校)時代に橋に興味があり、橋の腐食に関する数値解析、シミュレーションを行う研究室に入っていました。その後、大学院に進学するにあたり、面白そうなシミュレーションをしている研究室を探したところ、東大のコンクリートの研究室に出合いました。コンクリートのシミュレーションは複雑で難しく、ぜひ取り組みたいと思ったのです。以来、15年ほどコンクリートの研究に従事しています。
シミュレーションするためには、コンクリートのメカニズムを知る必要があります。計算機による解析だけでなく、実物を使った実験も行わなければいけません。実はコンクリートは、なぜ結合しているのか厳密には分かっていない不思議な素材です。当初はシミュレーションの対象でしたが、コンクリートそのものへの興味が高まり、研究を続けています。
――現在は、コンクリートのリサイクルに関する研究をされています。リサイクルに着目した理由は。
コンクリートのメカニズムを研究する中で、コンクリートを砕いた粉に力をかけると、塊(かたまり)になる性質に気づきました。コンクリートの瓦礫(がれき)を砕いて粉にし、それに力を加えると普通のコンクリートと同等以上の強度となり、追加処理によっては3~4倍の強度となることも分かりました。セメント成分が高圧で流動し、隙間を埋めて接着剤となることで固まっていると考えています。
そこからリサイクルに興味を持ち始めました。例えば昔のコンクリートには強度が低いものもあるのですが、砕いて固めると強いコンクリートに再生できます。この方法だとゴミが出ず、100%リサイクルできます。コンクリートのリサイクルについて調べてみたところ、世界でも進んでいないことが分かり、研究を進めるようになりました。
コンクリートを粉砕した粉を固めることで新しくコンクリートを作る技術は、5年ほど前に開発し、論文も書きました。現在は技術の核となる部分を特許として出願しているところです。
 リサイクルしたコンクリート。コンクリートに含まれるセメント分を接着剤とし、圧力をかけて作る。「地球上にある全てのコンクリート瓦礫を原料にすることができる」という
リサイクルしたコンクリート。コンクリートに含まれるセメント分を接着剤とし、圧力をかけて作る。「地球上にある全てのコンクリート瓦礫を原料にすることができる」という
――そうした循環型コンクリートについての研究は、社会にとってどのような意義があるでしょうか。
コンクリートは、砂・砂利と水、セメントを混ぜて作ります。ここにいくつかの問題が含まれています。
1つは、コンクリート瓦礫の処理です。建物などを壊した後のコンクリートは、瓦礫になります。日本では砕いてアスファルトの舗装の下に敷かれるなど再利用されることもありますが、海外では多くが埋め立てられています。リサイクルして循環できる方法がなかったからです。
もう1つは、コンクリートを作るときの環境負荷です。コンクリートの材料となるセメントの製造には1,450℃の高温加熱が必要で、その際に大量のCO2が排出されるのですが、これが世界のCO2総排出量の8%を占めるといわれています。コンクリートの粉を固めるだけであれば、セメントを使わずに済むのでCO2の排出を抑えられます。
さらに、砂・砂利の枯渇も課題です。採りやすいところからは採り尽くしつつあると同時に、海や川からの採取は環境保護の観点で規制されるようになってきました。

触媒を用いた脱炭素型コンクリート
――循環型コンクリートは、環境負荷の軽減につながるのですね。リサイクル以外にも、脱炭素の観点で進められているコンクリートの研究はありますか。
触媒を用いたコンクリートの代替材料の研究を進めています。具体的には、砂同士をくっつけてコンクリートにする技術です。普通のコンクリートは砂・砂利とセメント、水を混ぜて作りますが、その中の砂だけを使ってコンクリートを作ることができます。もう少し詳しく説明すると、現状では砂と触媒、アルコールを混ぜて約250℃で加熱すると、1晩ほどで塊が出来上がります。セメントを使わないので、CO2の排出量を抑えることができます。
砂漠の砂など低品質な砂でも建材を作れないか、という思いで始めた研究でもあります。品質の高い砂・砂利が採掘しにくくなっていることは、先ほどご説明した通りです。
それから、砂を使ったコンクリートにはもう1つメリットがあり、耐久性を高める効果も期待できます。普通のコンクリートはセメント分があるために酸で溶けたり、乾燥や収縮でひび割れたりしてしまいますが、砂同士をくっつけるコンクリートは岩を作っているようなものなので、うまくいけば何万年も使い続けることができると期待しています。現在の普通のコンクリートの代替品となる「次世代コンクリート」として、私自身も注目しています。
――どんな砂でもコンクリートを作ることができるのですか。
さまざまな砂で作ることができます。砂漠の砂のほか、珪砂(けいしゃ)*や月の砂でも作ることができます。本物の月の砂ではありませんが、同じ成分を持つ砂で開発を進めているところです。
砂だけでコンクリートを作れるということは、既存のコンクリートの材料が手に入らないところでもコンクリートを作れるようになるということです。例えば、砂漠に学校を建てるといったケースです。砂漠の中にある町までセメントや水を運搬するのは大変ですが、砂であれば現地にたくさんあります。あとはアルコールと触媒を持っていけば、建材が作れるわけです。同様に、月でもコンクリートの建造物を造ることができます。
その土地の砂の特徴を生かした建材を作ることができ、建材の地産地消という観点でも価値のある研究だと考えています。
*珪砂(けいしゃ):石英という二酸化ケイ素を主成分とした鉱物からできている砂。耐熱性や耐火性に優れている。
 左から砂漠の砂、月の砂の成分を模した砂、珪砂を使って作ったコンクリート
左から砂漠の砂、月の砂の成分を模した砂、珪砂を使って作ったコンクリート
※記事の情報は2022年1月5日時点のものです。

- 酒井雄也(さかい・ゆうや)
1984年生まれ、東京大学生産技術研究所准教授。2007年、豊田工業高等専門学校専攻科建設工学専攻修了。2011年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。その後、東京大学生産技術研究所で特任助教、助教、講師を経て2020年から現職。コンクリートの耐久性やリサイクル、コンクリートの代替材料などを研究している。
〈後編〉へ続く






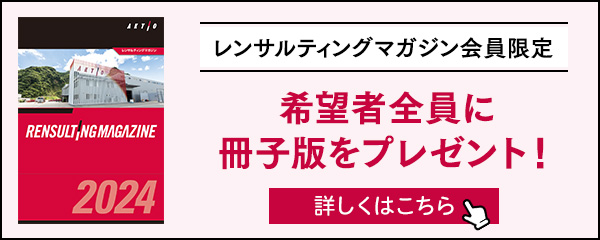













![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

