2022.04.20
【建設✕SDGs②】建設業界で働く女性をバックアップする「けんせつ小町」活動〈前編〉現場の"女子トイレ問題"は入口に過ぎない SDGsに掲げられている「ジェンダー平等」の観点から、建設業界でも性別を問わず働きやすい環境の整備が進められています。建設現場で働く女性の数は増加傾向にありますが、現場の女性を取り巻く環境には課題もあります。日本建設業連合会では、建設業界で働く女性を支援する「けんせつ小町」活動を展開。さまざまな施策を行っています。女性の就業の現状と課題について、「けんせつ小町」活動のとりまとめ役である本田一幸(ほんだ・かずゆき)氏にお聞きしました。
文:三上 美絵(ライター) 写真:安達 康介

女性技術者の比率は5.7%、約20年間で3.5倍に増加
――日本建設連合会(以下、日建連)*では、もっと女性が活躍できる建設業の実現を目指し「けんせつ小町」活動を展開されています。建設業で働くすべての女性を象徴する「けんせつ小町」という愛称はいつ、どのようにして決まったのですか。
2014年に公募したところ、約2700の案が寄せられました。日建連の当時の関係者がその中から決定したネーミングで、商標登録も行っています。その後2015年に「けんせつ小町」活動の実施主体となる「けんせつ小町委員会」を立ち上げ、建設業で働く女性たちの活躍支援を開始しました。
けんせつ小町委員会には「人材確保」「職場環境整備」「けんせつ小町支援」「広報」の4つの専門部会(2022年2月現在)があり、各活動について役割を分担して取り組んでいます。
*日本建設連合会(日建連):全国的に総合建設業を営む企業及び建設業者団体の連合会。2022年2月現在、正会員142社+5団体、特別会員6社で構成されている。

――「けんせつ小町」活動を立ち上げた背景には、どんな課題があったのでしょうか。
2013年に当時の安倍政権が成長戦略の柱の1つとして「女性活躍」を掲げ、産業界はこれを推進していくことになりました。人手不足の問題を抱える建設業界としても、多くの女性に入ってもらうことは大変意義のあることです。特に大手ゼネコンは、それ以前から危機感を持っており、2000年代中頃から女性技術者の採用を計画的に増やし始めています。
――当時、大手ゼネコンの建築設計などの部署には女性技術者の姿が見られましたが、現場には女性がほとんどいませんでした。それが現在では現場で施工管理を担う女性社員が珍しくなくなり、だいぶ変わってきた印象があります。建設業への女性の就業状況は、どのように推移していますか。
ゼネコンなど元請けで施工管理などを担う女性技術者の比率は、2000年の1.7%から2019年では5.7%と、約20年間で3.5倍に増加しました。今後も増加傾向は続くと考えております。事務職に占める女性の割合も19年時点で約40%となっています。日建連では会員企業に占める女性技術者の割合を、2024年までに10%まで伸ばすことを目標にしています。
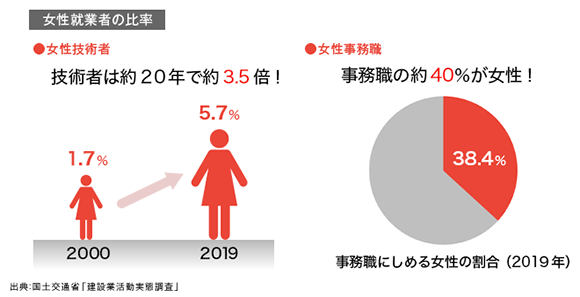
女性技能者が増えれば現場のトイレ問題は解決する
――「けんせつ小町」活動には専門工事会社などで働く「技能者」も含むそうですが、どの職種が増えているなどの傾向はありますか?
女性技能者は、2013年の8.2万人から18年には10.4万人と、5年間で1.3倍に増えました。女性技術者は同じ5年間で1.6倍に増えています。やはり現場に出る技能者は肉体的な問題もあり、技術者と比較すると伸びづらいのが実情です。それでも内装仕上げや左官工など細やかさが求められる職種は、多少増えやすい傾向にあります。
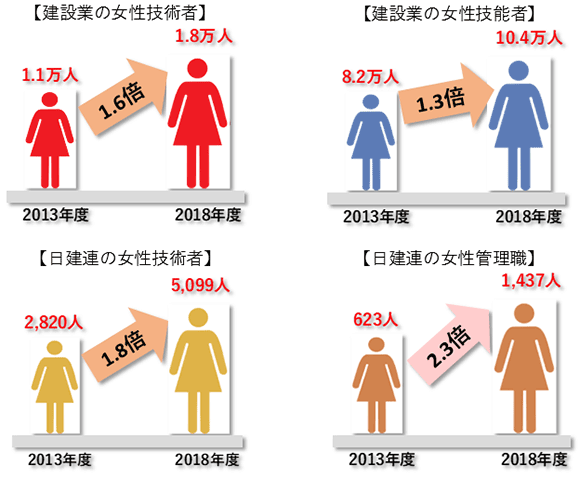 出典:【報告書】日建連の女性活躍推進に関する取組結果
出典:【報告書】日建連の女性活躍推進に関する取組結果
――女性技能者の数が伸びづらい背景には、どのような問題があるのでしょうか。
現場に出る仕事の場合、更衣室やトイレの問題もあります。そうした環境が整ってくれば女性技能者も入りやすくなる。それには元請けの協力が欠かせません。しかし元請けには、入場する協力会社に女性がいるかどうかは現場に仮設事務所を設置する段階では分かりません。協力会社のほうから「当社は女性技能者がいるので、女性用トイレ設置の経費を認めてほしい」と申告して認められるかどうかです。
けれども、元請けの施工管理者に女性が増え、またどの協力会社にも女性がいることを想定することができれば、最初から当たり前に女性用トイレが設置されていくはずです。その認識を変えていく必要があります。日建連では2024年までに現場での女性用トイレおよび更衣室の設置100%を目指しています。
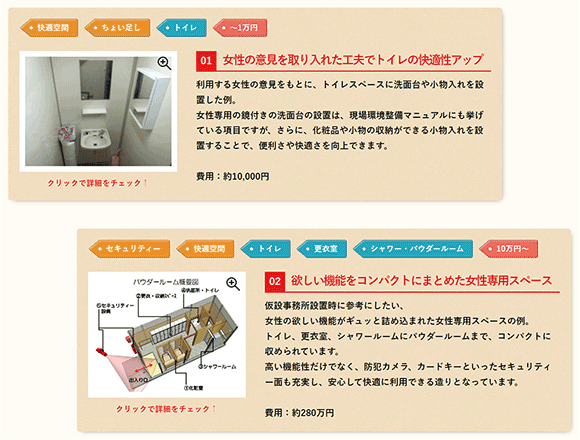 日建連のサイト内にあるけんせつ小町のページでは、働く環境をより良くするちょっとしたコツ・裏技(Tips)をまとめた「けんせつこまちっぷす」を掲載。その中で、トイレについての事例も紹介している
日建連のサイト内にあるけんせつ小町のページでは、働く環境をより良くするちょっとしたコツ・裏技(Tips)をまとめた「けんせつこまちっぷす」を掲載。その中で、トイレについての事例も紹介している
――近年は、性別を問わず誰でも利用できる「オールジェンダートイレ」を設置する動きも活発化していますね。
男性にとっても使いやすいトイレの設置が進むのは良いことです。建設業界全体が発注者も含めてそうした価値観、文化になれば、この問題は解決するでしょう。
そのためには、男性の目線だけでは気づけないことがあります。例えば、ある現場を訪れた際、トイレに小便器がついたてがないまま、むき出しで設置されていました。現場の女性から「どう思います? これ」と指摘されて、はっとしたんです。奥の個室に入るためには、必ずそこを通らないといけません。動線に配慮するなど、男には思いつかない。そういうことはトイレに限らずたくさんあります。
実は私自身、以前は環境部で現在のSDGsに関するCSR・環境経営の推進に関する業務を担当していましたが、「ジェンダー平等」について深くは理解できていませんでした。そんな中、今の部署にきて現場の女性活躍推進の話題になると、すぐにトイレの話になることに違和感もありました。
トイレ問題は目に見えるので、話題になりがちです。しかし、トイレは業界の課題の入口を象徴しているに過ぎません。大事なのはトイレを改善するだけでなく、男女ともに働き続けられる文化をつくること。それが日建連の「けんせつ小町」活動の本質でもあります。

――「けんせつ小町」活動により、女性の入職は少しずつ増えてきました。現状の課題、テーマは何でしょうか。
2014~2019年の5年間は、特に「入職」に力を入れ、建設業で働く女性たちの活躍支援を行ってきました。それを踏まえ、2019年11月に次の5年間の新計画である「けんせつ小町活躍推進計画」を策定しました。柱となるテーマは「定着」「活躍」「入職」支援です。この3つを軸に、「誰もが『働きやすい』『働きつづけたい』と思う建設業界をめざす」。それが新計画のコンセプトです。
最初に「定着」を持ってきたのは、「結婚や出産などのライフイベントが影響して仕事を続けられず、辞めていってしまう現状を変えていきたい」という声が委員会から上がったためです。それに、せっかく建設の仕事がしたくて入職してもすぐに辞めてしまう環境では、バケツに穴が開いているようなものです。
今いる人が「定着」して「活躍」できる。持っている力を発揮でき、例えば子育てしながらでも現場で働き続けられるようにする。そのような基盤が整えば、「入職」も自然に増えていくと考えます。
大手ゼネコンなどでは現在、技術者採用で性差の偏りはなくなってきており、女性の「入職」はすでに当たり前になりつつある。大手がそのように変われば、やがて準大手の会社にも変化が波及していきます。また元請けで女性の現場監督が増えれば、専門工事会社の女性技能者も間接的に増えていくでしょう。そういう好循環が生まれることを期待しています。
※記事の情報は2022年4月20日時点のものです。

- 本田一幸(ほんだ・かずゆき)
2006年、一般社団法人日本建設業団体連合会(現日本建設業連合会)入社。2015年まで同連合会の環境部「建設業の環境自主行動計画」の策定・改訂、「建設現場における温暖化対策」等を担当。2016年から企画調整部「けんせつ小町」活動におけるさまざまなプロジェクトを手掛ける。
〈後編〉へ続く




















![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

