2025.11.07
インフラを支えるコンクリートの魅力とは? 万能建材ながらその原理は未解明【次世代の建設資材①コンクリート 前編】 インフラ整備に欠かすことができないコンクリート。圧縮には強いが、引張に弱いという力学的な性質を補う必要から、引張に強い鉄筋と組み合わせて使用されることが多い建設資材です。昨今は、インフラ老朽化問題でも、注目が高まっています。コンクリートとはどのような建設資材なのか。その特徴と課題を、東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科教授の加藤佳孝(かとう・よしたか)氏に聞きました。
文:茂木 俊輔(ジャーナリスト) 写真:鈴木 拓也

安さと調達の手軽さがコンクリートの強み
──コンクリートはインフラ整備に欠かせない建設資材です。資材としての特徴はどこにありますか。
コストの低さと調達の手軽さです。輸送費の値上がりもあって、今でこそ立米単価は2.5万円ほどですが、ほかの建設資材と比べてもその安さは決定的な強みです。また、国内どこでも手に入りやすい水とセメントと砂・砂利などの骨材を混ぜてつくるので、手軽に調達できます。この点も結果として、コストの低さにつながっています。大量に使うことにも抵抗がありませんから、ダムのような巨大な構造物の建設資材にも向いています。
型枠さえあれば、現場で自由に成形できるのもコンクリートの魅力です。鉄骨は工場で生産したものを組み立てるだけですが、コンクリートは現場で任意に成形できます。しっかり施工すれば、コンクリートは大きく劣化しない。理論的には1000年ほど保たせることも可能です。
──コンクリートは、国内ではいつぐらいからインフラ整備に使用されてきたのですか。
明治時代には国営会社でセメントを供給していました。今思うに、島国の日本では諸外国との貿易に欠かせない港湾の整備が求められていました。海の近くに整備するわけですから、当然、さびやすい鉄骨は不向きです。そこで、コンクリートの出番が自ずと生まれたのでしょう。
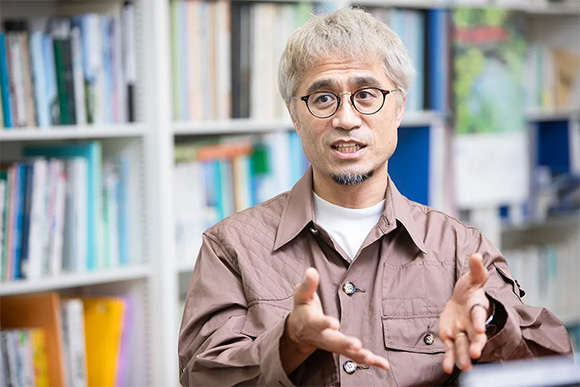
──それ以来、コンクリート製造の根本は変わっていないのでしょうか。
はい。廃棄物や産業副産物を有効利用していこうというのが、コンクリート製造の基本にあります。コンクリートの構成物質のひとつである「普通セメント*1」の製造には、廃プラスチック、廃油など多くの廃棄物をはじめ、産業副産物も有効利用される一方、その製造過程では大量のCO2を排出します。そのため、普通セメントの一部を製鉄工場の副産物である高炉スラグ*2や、石炭火力発電所の副産物であるフライアッシュ*3に置き換えることでCO2排出量を削減したセメントも開発されてきました。これらの技術はすでに確立されており、JIS(日本産業規格)でも規格化されています。
*1 普通セメント:ポルトランドセメントとも呼ばれ、石灰石、粘土、珪石などが主な原料となる。これらを混合・粉砕し、焼成してクリンカーを製造後、石膏とともに微粉砕してつくられる。
*2 高炉スラグ:製鉄の過程で高炉から生まれる鉄以外の成分。
*3 フライアッシュ:石炭火力発電所で石炭を燃焼する際に発生する微細な石炭灰のこと。
それでも、これら産業副産物を利用したセメントは再生紙のようには普及しません。現状で言えば、普通セメントが市場流通量のおよそ8割を占めるのに対し、普通セメントの30~60%程度を高炉スラグに置き換えた「高炉セメントB種」と呼ばれるものは、2割程度にすぎません。普通セメントの一部をフライアッシュに置き換えたものに至っては、市場流通量における割合はごくわずかです。
もちろん、これらは普通セメントと遜色ない性状を持つセメントとして開発されてきました。しかし、普通セメントはもともと安価なものなので、あえて産業副産物を利用する必要に迫られません。また、産業副産物を利用した高炉セメントB種を使うよりも、「普通セメントを使った方が品質がいい」という印象が根強くあったため、あえて高炉セメントB種を選ぶことがなかったのでしょう。
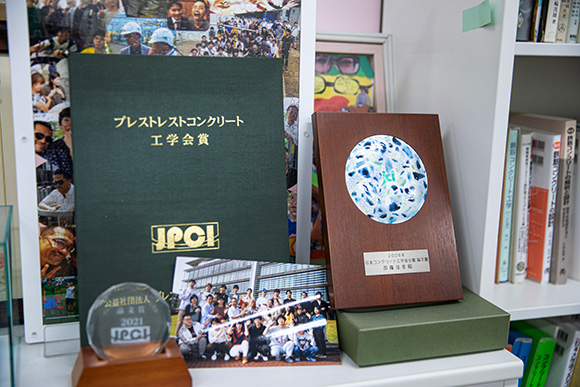 プレストレストコンクリート技術の進歩・発展に顕著な貢献をしたと認められる個人や団体に授与されるプレストレストコンクリート工学会賞(論文賞)など、これまで多くの賞の受賞歴がある
プレストレストコンクリート技術の進歩・発展に顕著な貢献をしたと認められる個人や団体に授与されるプレストレストコンクリート工学会賞(論文賞)など、これまで多くの賞の受賞歴がある
コンクリートの劣化が急速に社会問題化
──先ほど、「コンクリートは劣化しない」と説明されましたが、現実にはコンクリートの劣化に伴うインフラの老朽化が社会課題となっています。なぜこのようなギャップが生じてしまうのですか。
劣化しないというのは、あくまで施工が丁寧に行われた場合の話です。ところが実際には、そうはいきません。まず高度経済成長期におけるインフラ整備の問題です。例えば、首都高速道路であれば、1964(昭和39)年の東京オリンピックの開催に間に合わせる必要がありました。丁寧な施工より工期の厳守が優先された可能性があります。
次に劣化の想定がなかったという問題もあります。実は、コンクリート構造物はもともと、メンテナンスフリーと考えられていました。ところが1984(昭和59)年にNHKで放映された報道番組「コンクリート・クライシス*4」をきっかけに、コンクリートの劣化が急速に社会問題化していきました。
*4 コンクリート・クライシス:当時のコンクリート構造物の早期劣化問題を告発し、技術者や社会に警鐘を鳴らした報道特集番組。この報道をきっかけにコンクリートの品質問題が国民の大きな関心を呼んだ。
当時は、今では当たり前のルールも存在しませんでした。例えば、コンクリート中の塩分総量の規制です。骨材事情の悪い関西の場合、海の砂を使うこともありますが、海の砂には鉄筋が腐食する主要因のひとつである塩化物イオンが含まれています。もし鉄筋の腐食が進行すれば、鉄筋コンクリートとしての耐力が低下してしまいます。
今は塩分総量規制で定められた条件を満たして初めて骨材として使えますが、当時はルールがなかったため、海の砂でも塩分総量に関わらず使うことができた、という事情があります。
──コンクリートの劣化には、塩害のほかにどのような原因がありますか。
質の悪い骨材を使うと、アルカリシリカ反応が起きる恐れがあります。これは骨材に含まれるシリカ鉱物とコンクリート中のアルカリが反応し、アルカリシリカゲルが生成される現象です。このアルカリシリカゲルは水分を吸収し膨張するため、その圧力でコンクリートにひび割れが生じます。シリカ鉱物を含む骨材を避けるのが一番ですが、骨材の原料の多くは自然物ですから100%は避けきれないのが実情です。
もうひとつ深刻なのが、硫酸による下水道管の化学的劣化ですね。コンクリートも鉄筋も酸に弱いだけに、劣化が進むと崩壊することさえ考えられます。2025年1月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故も、この化学的劣化による下水道管の破損が原因とされています。
厄介なのは、コンクリートを修復しようにも、人が立ち入れない点です。下水道管は古いものであれば、管径がそう大きくない。人ひとり入れるかどうかです。管内は狭く、しかも暗い。さらに有毒なガスも発生しています。こんな環境では、問題の所在を見極めるのさえ、非常に困難です。

──コンクリート構造物は、劣化の状況を見極めるのも厄介そうです。
そうですね。鉄骨であれば、問題になるさびはその表面に生じます。裏返せば、その防止には、鉄骨の表面に塗膜をつくればいいわけです。ところが、コンクリート構造物は、その内部で劣化が進行していることがあります。鉄筋がさびて膨張することで引き起こされる問題も、外からは見えません。費用を投じて調査しないと健全性を評価できないという弱点を抱え、維持管理が難しいです。
カーボンニュートラルへの対応で、コンクリートの原理原則を解き明かす必要が出てきた
──コンクリートを研究されてもう30年以上とお聞きします。建設資材としての面白さは、どこにあるのですか。
実は原理原則が分かっていないんです。例えば、化学混和剤の働きです。コンクリートは、材料を練り混ぜたものを型枠内に流し込み、化学反応で固めます。固まるまでのものをフレッシュコンクリートと呼びます。その性状を改善する目的で気泡を加えるために混入するのが、混和剤です。ただ、混和剤を混ぜると、なぜコンクリートに気泡が加わることになるのか、メカニズムは明らかではありません。
これまでは、そのメカニズムが分からないままでも済みました。材料の配合を変えながら試行錯誤を重ね、結果として求める性状を持つコンクリートを生み出してきたからです。原理原則は分かっていなくても、何ら支障はなかったのです。
ところが、これからはそうはいきません。それは、カーボンニュートラルがこれまで以上に求められる中、普通セメントの使用量を減らしてCO2の排出量を抑えようとする動きが活発になっていく、と見られるからです。
普通セメントの代わりに、さまざまな材料が登場してくるでしょう。その度に試行錯誤を重ねていたのでは、膨大な量の実験が必要になります。それは、現実的ではありません。試行錯誤を重ねなくても技術開発に臨めるように、原理原則を解き明かす必要があります。
※記事の情報は2025年11月7日時点のものです。
【後編】へ続く
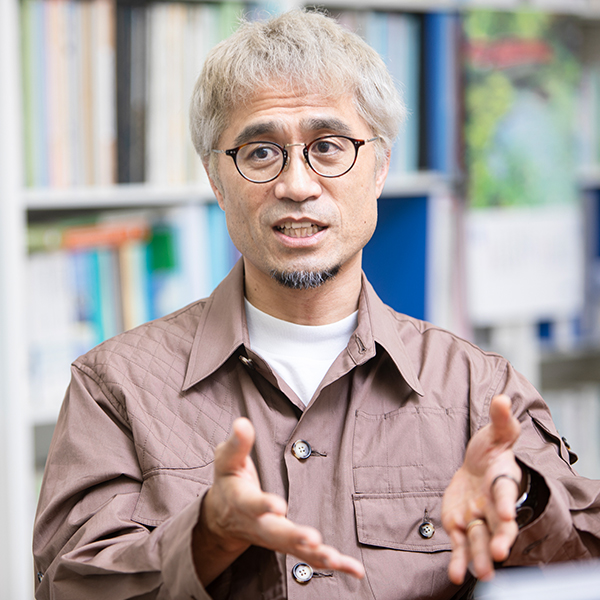
- 加藤佳孝(かとう・よしたか)
1971年生まれ。東京理科大学創域理工学部社会基盤工学科教授。1990年、県立静岡高校卒業後、東京大学理科一類に進学。1994年、同大工学部土木工学科卒業。1999年同大大学院・工学系研究科の博士号(工学)取得。国土交通省国土技術政策総合研究所、東大生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センターを経て2011年、東京理科大学理工学部土木工学科(現・創域理工学部社会基盤工学科)准教授に就任。2016年より現職。専門はコンクリート工学と建設材料マネジメント。
〈アクティオの商品情報〉




















![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

