2023.07.26
LEED認証で築く人と環境に優しい賃貸住宅〈後編〉高気密・高断熱賃貸住宅が次世代は「当たり前」に【建設×SDGs⑦】 2023年2月に埼玉県和光市に完成した、「LEED(リーダーシップ・イン・エネルギー&エンバイロメンタルデザイン)」認証制度を指標として導入した賃貸住宅「鈴森village(ビレッジ)」。そもそもLEED認証制度とはどのような制度で、取得するには何が必要なのでしょうか。後編では、設計・監理を担当した建築家の三浦丈典(みうら・たけのり)さんに、今回のプロジェクトの進め方や、これから日本でLEED認証が広がる可能性などについて、うかがいました。
文:池谷 和浩(ライター) 写真:安達 康介

LEED認証のような評価制度はこれから必ず重要になる
――住宅の性能を評価する制度はほかにもありますが、鈴森villageでは、なぜLEED認証制度を採用したのですか。
これは発注者・所有者の、決意とも言うべき強い意向でした。クライアントは、この敷地を含む土地を代々受け継いできた土地所有者である鈴木家のご夫婦です。ご主人の鈴木晴紀(すずき・はるのり)さんは僕と同じ早稲田大学理工学部建築学科の出身で、僕の講演を聴きに来てくれたのがきっかけでした。
 省エネ・環境設計の理想を目指す「LEED認証制度」を申請した「鈴森village」。周辺住民も通り抜け可能な通路に面し、各住戸にアウターリビングを配した(©中村晃)
省エネ・環境設計の理想を目指す「LEED認証制度」を申請した「鈴森village」。周辺住民も通り抜け可能な通路に面し、各住戸にアウターリビングを配した(©中村晃)
実は晴紀さんは当時、重い病を患っていて、代々引き継いできた土地をしっかりとした資産として受け渡さなければならないと、自分が亡き後も安心してそれを託せる担い手を探していたのだそうです。ですから、このプロジェクトは単に「賃貸住宅を建てたい」というものではないんです。代々続く土地というタスキを次世代へつないでいきたいという思いが根本にあります。
そこでまず、経営資産管理の専門家とプロジェクトチームを組み、鈴木家の事業計画を煮詰めていきました。その後、敷地全体のキャッシュフローをどのように計画するか、一部を駐車場とし、一部を賃貸住宅とし、総建設費用、資金調達額といった事業計画を決めました。
そうして想定のボリュームを振り分け、3階建ての建物を敷地内に分散配置するという基本計画が定まり、晴紀さんにはその模型まで見届けていただきました。
計画を実施設計に移行していくに当たって、晴紀さんはこう言い遺していたんです。「LEED認証のような評価制度はこれから必ず重要になるので、賃貸住宅経営に乗り出すからにはそうした制度を使った方がよい」と。晴紀さんが、個人所有の不動産というものにどのように価値を付けるか、ずっと考え抜いた結論でした。
 鈴森villageの1階壁面に描いた配置図。地域に根ざす旧家として、明治期には村長も輩出した代々の鈴木家当主がシルエットのモチーフになっている(©中村晃)
鈴森villageの1階壁面に描いた配置図。地域に根ざす旧家として、明治期には村長も輩出した代々の鈴木家当主がシルエットのモチーフになっている(©中村晃)
高層建築も可能な土地で、あえて3階建てに
──LEED認証について、具体的に教えてください。
LEEDの基本的な評価軸は、大まかに6つあります。敷地、水、エネルギー、資材、室内環境、革新性を個別に評価します。
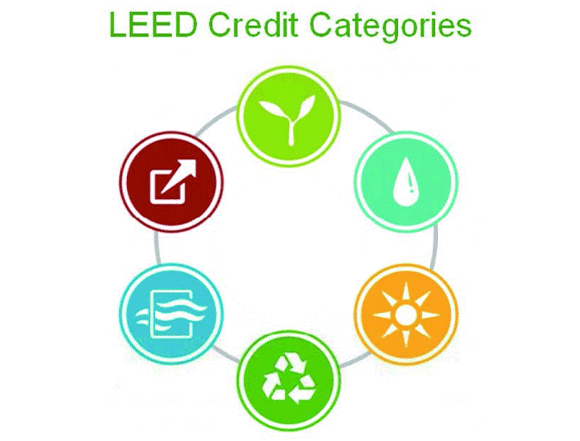 LEED評価制度の評価軸。敷地の選定から水の利用、周辺環境を含めたエネルギー対策などがある。室内環境の快適性や健康性はその評価要素のひとつだ(資料提供:スターパイロッツ)
LEED評価制度の評価軸。敷地の選定から水の利用、周辺環境を含めたエネルギー対策などがある。室内環境の快適性や健康性はその評価要素のひとつだ(資料提供:スターパイロッツ)
評価はCERTIFIED(標準認証)からプラチナまでの4段階に分かれています。必須で満たすべき条件をクリアした上で、「より環境に良い」要素を積み上げ加点していく仕組みで、ベースとなる認証のハードルがとても高いのが特徴です。最上位のプラチナを得るためには、恵まれた敷地環境と大規模なスケールの投資が必要になります。今回のプロジェクトはこの仕組みを首都圏の民間賃貸住宅に活用するというコンセプトですから、当初からベースのCERTIFIEDをターゲットとしました。
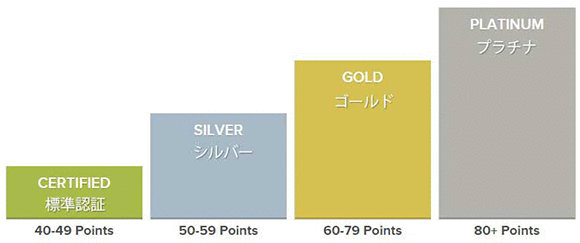 LEED認証の4レベル。計画において取り組んだ環境配慮要素をそれぞれポイントとし、加点方式で積み上げる仕組みだ。「必須項目」を満たした上で、ポイント取得状況で認証レベルが決まる。(出典:一般社団法人グリーンビルディングジャパン)
LEED認証の4レベル。計画において取り組んだ環境配慮要素をそれぞれポイントとし、加点方式で積み上げる仕組みだ。「必須項目」を満たした上で、ポイント取得状況で認証レベルが決まる。(出典:一般社団法人グリーンビルディングジャパン)
最初からハードルを上げて難しいと諦めてしまうのではなく、標準レベル(CERTIFIED)であれば民間事業者でも採算を取ることができる。そのことを実証して世の中に伝えていくことが、本プロジェクトの使命だとも考えています。
──具体的には、どのような評価項目があるのですか。
最初の要素は敷地要件です。一定距離以内に小学校や文化施設があるか、そもそも人が豊かに暮らすのに適した場所か、などといった点です。今回の敷地はまさにこの要件を満たす場所で、これはクリアできました。
LEED認証は単なる認証制度ではなく、その根底に「フィロソフィー(哲学)」があるのもユニークな点です。建物単体が高性能であるだけでは不十分で、地球環境にとって良い建物である必要があるのです。まさにSDGs(持続可能な開発目標)の視点とも合致しますね。LEEDはアメリカにおいて不動産の資産価値に直結している制度ですから、LEED for Homesの枠組みにも、資産価値のある住宅や住宅地とはそうしたものだというフィロソフィーが織り込まれているわけです。

定量的な評価のため数値を重視するLEED認証
――実施設計や施工ではどのような点が重要なのですか。
建築計画を具体的な形にしていく上でも、さまざまな評価軸があります。水の利用という面では、雨水を灌漑(かんがい)利用して電動ポンプなどは一切使わず植栽の根元へ引き込んでいます。水が貴重な資源のひとつだと認識されているアメリカでは特に重要な項目です。もちろん日本でも賃貸住宅経営のコスト抑制につながります。
 住戸を結ぶ屋外通路にもふんだんに植栽を配した。雨水を植栽の根元やプランターに導いた(©中村晃)
住戸を結ぶ屋外通路にもふんだんに植栽を配した。雨水を植栽の根元やプランターに導いた(©中村晃)
──気密性の評価はどのようにチェックされるのでしょうか。
最終的にアメリカから評価者(レイター)が来て、何部屋かを実測し、その結果を基に全体を評価するというプロセスを経ます。どこでテストを行うかは当日まで確定しないので、事前に全住戸で性能が確保されているかを確認する必要があります。これは窓を閉め切り、専用機材を使って居室内を負圧にして、内外気圧差から「隙間相当面積」を測るものです。「気密測定」という、いわゆるリークテストです。この試験は国内の協力先が担当しました。
気密工事は施工者の作業者、施工管理者と一緒になって取り組みました。気密性は建物内外を仕上げる前工程である躯体(骨組み)工事で決まり、仕上げが終わると手直しができません。評価者が来るのはそうした仕上げが完了した後ですから、これは緊張しました。
例えば木造部分では躯体に構造用面材を取り付けた後、目地をテープで目張りしたり、取り合いを発泡系材料で埋めたりします。オフィスなどとは違って、住宅は小さな空間が曲がりくねって出来ているので、出隅や入り隅がたくさんありますよね。板と板がぶつかる角の部分ですから、特に気密が確保しにくいのですが、設計・施工者総出でそうしたポイントを探し出していきました。
 木造部分の気密工事では、隙間となる材料の取り合い部分に発泡系材料を充填するなどの必要がある。右下の写真が気密測定に使う専用機材(写真提供:スターパイロッツ)
木造部分の気密工事では、隙間となる材料の取り合い部分に発泡系材料を充填するなどの必要がある。右下の写真が気密測定に使う専用機材(写真提供:スターパイロッツ)
不動産投資における新たな指標
――これはLEED認証ならではの工夫なのですか。
LEEDだからというわけではなく、居室の省エネ性や快適性を突き詰めていくと、こういう形にならざるを得ないんです。こうした設計・施工は、日本では戸建てを中心に「高気密・高断熱住宅」というひとつのジャンルとなっていますが、東京近郊や大阪近郊といった大都市圏の賃貸住宅ではまだ普及が進んでいません。現在の日本の賃貸住宅としては、希少価値があるのは間違いないでしょうね。日本では「2050年カーボンニュートラル達成」が社会目標となっていますから、今後はこうした設計・施工をさらに広く採り入れていく必要があるでしょう。
日本の住宅分野で省エネ基準が機能し始めたのは、意外に最近のことです。ですが今後は、そうした暖かく涼しい家で育った子どもたちが成長し、1人暮らしをしたり家族を持ったりするようになります。賃貸住宅が永続的に資産価値を保つには、そんな将来の顧客を見据える必要も出てきます。駅から徒歩何分という立地要件は絶対に変えられず、その市場で新しく建つ住宅と常に競争し続けるのですから。不動産投資における新たな指標として、LEED認証はとても良い仕組みだと思います。
※記事の情報は2023年7月26日時点のものです。

- 三浦丈典(みうら・たけのり)
建築家、一級建築士事務所 株式会社スターパイロッツ代表
1974年東京都生まれ。2007年設計事務所スターパイロッツ設立。大小さまざまな設計活動に関わる傍ら,シェアオフィスや撮影スタジオも経営。 日本各地のまちづくり、都市経営、公民連携事業にも携わる。「道の駅FARMUS木島平」で2015年グッドデザイン金賞を受賞。 著書に「起こらなかった世界についての物語」、「こっそりごっそりまちをかえよう。」、「いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ」(以上、彰国社刊)など。
スターパイロッツHP:https://www.starpilots.jp/






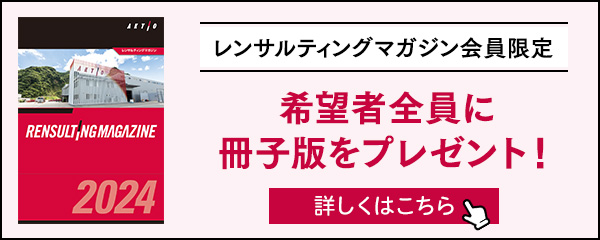













![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

