2021.10.20
【建設でがんばるヒント 第3回】現場の問題を0(ゼロ)にするコミュニケーション技術 その3 建設技術コンサルタントとして活躍する降籏達生さん。主宰するメールマガジン「がんばれ建設~建設業専門の業績アップの秘策~」でも健筆をふるわれています。本連載では、降籏さんに建設業界で生き生きと働くためのヒントをご教示いただきます。第3回は、建設工事現場で必要な現場コミュニケーション5つのポイントのうち、交渉力について解説していただきます。
文:降籏 達生(ハタ コンサルタント株式会社社長)
カバーフォト:Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com
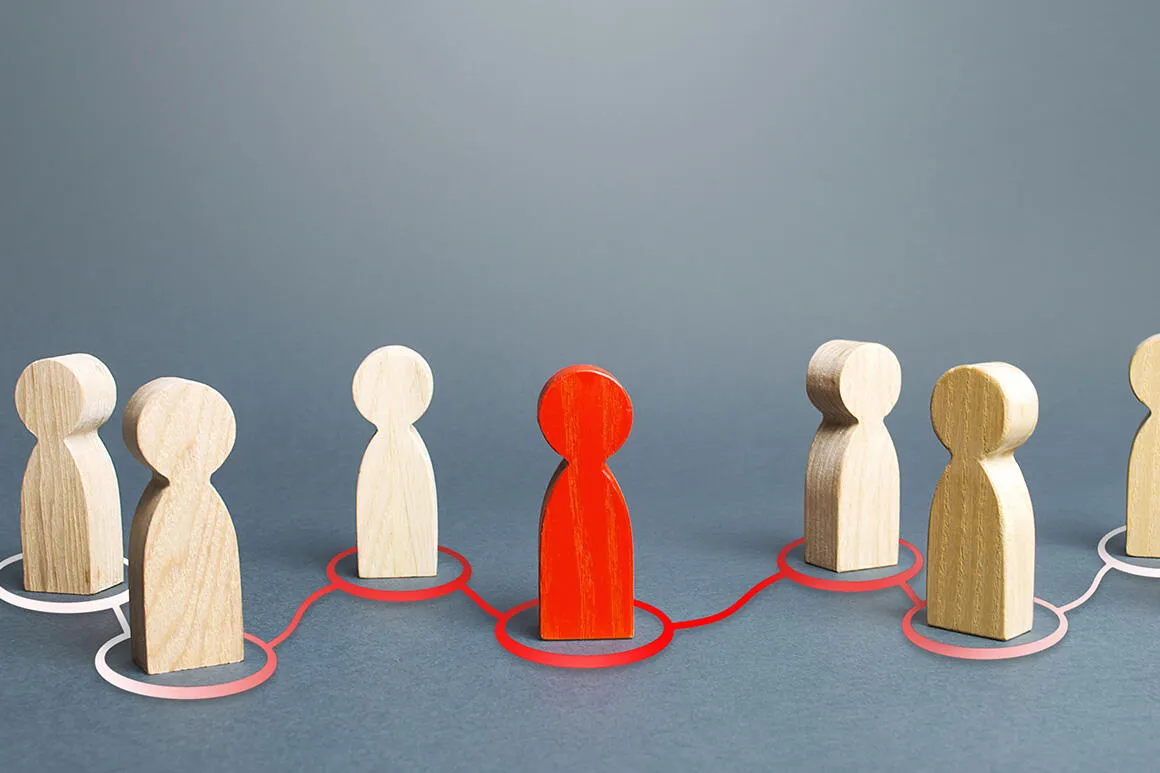
交渉を有利に進めるためのコミュニケーション術
現場代理人の職務は、下図に示すように顧客、協力会社、近隣住民、利害関係者とのコミュニケ―ションを取ることが重要な責務である。
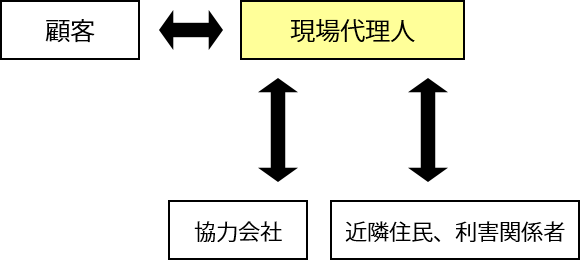
このコミュニケーションの中では、相手に対してこちらから要求したり、相手からの要求に対応したりすることに対して、葛藤が発生することもある。これに対してお互いが納得のいく形で交渉をまとめる能力を交渉力という。
今回は、交渉力をいかにして高めるかについて考えてみよう。
1.説得しないで共に勝つ
交渉の基本は、説得しないで共に勝つということだ。相手を交渉で打ち負かしてもいつの日か仕返しされる。逆に相手に打ち負かされるといやな気分が残ってしまう。 いかにして両者の利害を調整して、双方が自発的に合意する形にするのかということが重要だ。
2.交渉に勝つ自分を作る
1)アサーティブに伝える
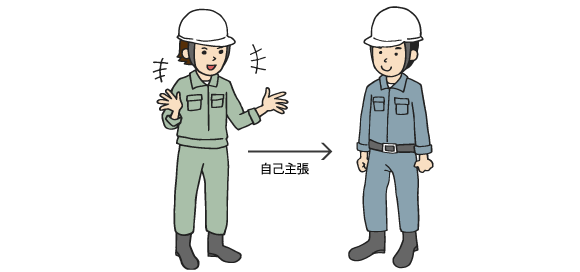
交渉力を高めるためには、まずは当方の思いを率直に伝えることが大切だ。伝えたい相手にしっかり自己主張することを、アサーティブ(Assertive)コミュニケーションという。アサーティブとは、表明する、主張する、の意味である。しかし多くの場合、その主張が強すぎたり(アグレッシブ)、弱すぎたり(パッシブ)して相手にきちんと伝わっていない。
「アグレッシブ」は攻撃的。アグレッシブな人は言いたいことはなんでも言うし、誰にでもストレートに表現してしまう。仲間からの頼みであっても無下に断ってしまうので、「もう、あなたには頼まない」といって人が離れて行ってしまうこともある。
「パッシブ」は受身的。パッシブな人は仕事の依頼を断りたいのに、まわりくどく言ってしまう。仕事を頼む際にもはっきり言わないので、相手には何をして欲しいのか伝わっていない。
アサーティブな交渉と、アグレッシブ、パッシブな交渉との違いを以下の表にまとめた。
| アグレッシブな交渉事例 | アサーティブな交渉事例 |
|---|---|
| 過去の話を持ち出す=「だいたい」「そもそも」「いつも」 例:以前の工事で失敗されましたね。だから今回は値引きをしてください。 |
いま、この時点、この場所での話として伝える。 例:この案件をぜひとも受注したいので、コストダウンのご協力よろしくお願いします。 |
| マイナスの言葉が多い=「ダメだ」「忙しい」「できないだろう」 例:この金額では到底納得できませんよ。 |
「できる」「やれる」などのプラスの言葉で伝える。褒める、感謝する。 例:いつもいい仕事をしていただいているので、ぜひとも貴社に発注したいのです。 |
| 「Youメッセージ」で相手を全否定する=「あなたは......だからダメなんだ」 例:あなたの会社で努力していただき、値下げをお願いします。 |
「私は......と感じるよ」と、「Iメッセージ」で伝える。 例:私も厳しい単価だと感じます。そこをなんとかご支援よろしくお願いします。 |
| パッシブな交渉事例 | アサーティブな交渉事例 |
|---|---|
| 前置きや言葉のクッションが多い=「幸いです」「なにとぞ」「ご多忙のところ」「すみません」 例:ご多忙のところ見積作成していただき、本当にすみません。 |
「えー」「あのー」は飲み込み、感謝の気持ちを表す。 例:見積作成、ありがとうございました。 |
| 言い訳が多い=「うちの上司が......」「会社では認められていないので......」 例:貴社の見積金額では、上司を納得させられないので......。 |
言い訳を飲み込み、自分の言葉で話す。 例:貴社に発注するよう私から上司に進言しますので、もう少しコストダウンをお願いできませんか。 |
| 相手の表情、反応を見ていない。 例:下を向いて、紙を見ながら話す。 |
投げたボールの行方を見届け、戻ってきたボールを使って次のボールを投げるようにする。 例:相手の目を見て話す。 |
2)ハロー効果を活用する

ハローとは後光という意味だ。人は、後光が差している人物をすごいと思い込んでしまうところがある。例えば、取得の難易度が高い資格(医師、弁護士、博士、一級建築士、技術士など)を持っているなど。
一級建築士や技術士などに挑戦したり、社会人大学院などに挑戦しMBAを取得したり努力することでハロー効果を得て、交渉を有利に進めることができるようになる。
3)決してあきらめない自分を作る~そこを何とか×3

これは、困難な状況にもかかわらずうまく適応する過程や能力のこと。「決してあきらめない」能力ともいえる。この能力の持ち主は、感情の安定性が高い。
通常、いやなことがあれば「私はだめな人間だ」と落ち込み、よいことがあると「私は天才だ」と高揚するものだ。しかし、感情の安定している人は、すぐに平静になることができる。ピンチの時に登板したリリーフ投手が平然と投球する姿を見ると、レジリエンス(復元力、回復力)の高さを感じる。スポーツ選手には欠かせない能力だ。
決してあきらめない能力を高めるためには、「そこを何とか」を3回言うようにするとよい。例えば、顧客と変更増額の交渉をする場面だ。
顧客「1000万円の増額は認められません」
施工者「そこを何とか、増額をお願いします」
顧客「認めるとしてもせいぜい500万円ですね」
施工者「500万円ですか。そこを何とか1000万円の増額をお願いします」
顧客「では中をとって750万円でどうですか」
施工者「750万円ですか。そこを何とか1000万円の増額をお願いします」
顧客「分かったよ。そこまで言うのなら1000万円の増額を認めます」
4)人間的魅力を身につける
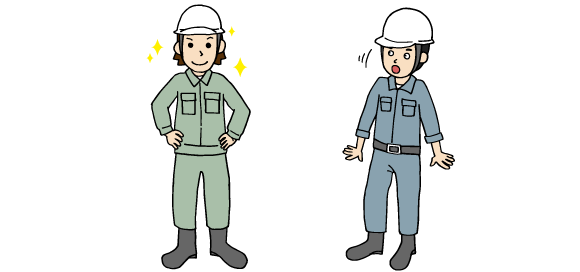
同じことを言われても、「あの人に言われたなら納得してしまう」という人がいると思えば、「あの人には言われたくない」という人もいる。これは人間的魅力が影響する部分が大きい。
木鶏(もっけい)という言葉がある。どのような闘鶏が真に強い鶏かという話である。相手に対して空威張りして闘争心があったり、いきり立っていたり、目を怒らせて己の強さを誇示しているようではまだまだだ。相手の闘鶏が鳴いても全く相手にせず、まるで木で作られた鶏のように平然としていると、戦わずして勝てるようになる。これが木鶏だ。
横綱双葉山が69連勝の後に破れたとき、「われ、いまだ木鶏たりえず」と話したことは伝説的に語られている。
人間的魅力を身につけた人は相手に惑わされることなく、ただ座っているだけで多くの人たちの模範となり、人を説得し、納得させてしまう。一朝一夕にそれを得ることは難しいことだが、故事や古書を学び、それを実践することで木鶏に少しでも近づきたいものだ。
※記事の情報は2021年10月20日時点のものです。

- 降籏 達生(ふるはた・たつお)
ハタ コンサルタント株式会社代表取締役。1961年生まれ。大阪大学工学部土木学科卒業後、株式会社熊谷組に入社。トンネル工事、ダム工事、橋梁工事に従事する。1995年阪神淡路大震災を目の当たりにして開眼。ハタコンサルタント株式会社を設立し、技術コンサルタント業を始める。実績は建設技術者研修20万人、現場指導5000件を超える。「がんばれ建設~建設業専門の業績アップの秘策~」は読者数20,000人、日本一の建設業向けメールマガジンとなっている。




















![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

