2024.09.20
省エネ、自動化の時代。国産建機は安定成長へ(前編)|建機の歴史⑤ 日本の国土開発、災害復興を支えてきた国産の建設機械を、それらが生産された時代背景とともに紹介する連載「建機の歴史」。第5回は、長く続いた高度成長期が終わりを告げ、さまざまな変化が訪れた1970〜1980年代が舞台です。技術力が急速に向上した国産建機は活躍の場を広げ、建機メーカーは新たに省エネや公害対策という課題にも取り組んでいきます。
文:萩原 美智子(ライター)

「列島改造ブーム」で建設業界はにわかに活気づく
1970(昭和45)年9月、「蛍の光」が流れる中、人々に多くの感動と驚きをもたらした日本万国博覧会(大阪万博)が閉幕した。国内には祭りの後のムードが漂い、経済活動は停滞の時期にさしかかる。
1971(昭和46)年8月には、世界経済に重大な影響を及ぼしたドル・ショックが発生した。米国のドル防衛策がきっかけで、為替市場は1ドル=360円の固定相場制から変動相場制へと移行。日本国内では、固定レートで安定した市場を形成していた中小企業などが深刻な打撃を受けた。
しかし、1973(昭和48)年、日本経済は「列島改造ブーム」で再び色めき立つ。ブームの源は、1972(昭和47)年12月に内閣総理大臣に就任した田中角栄の著書「日本列島改造論」だ。
計画の主旨は、高速道路網、高速鉄道網などを駆使して日本列島の主要地域を網羅する"一日経済圏"の実現。太平洋ベルト地帯に集中する工業の地方分散や、地方都市の整備を行うことで、全国の地域格差および過疎と過密を解消するというものであった。
このブームに刺激され、建設の世界では道路建設、住宅地やゴルフ場の造成、資源開発など工事の大規模化が目立つようになった。
大規模工事が増加し、建機の大型化が進むも列島改造計画は凍結
大規模工事が増えると、建機では大型機種へのニーズが高まっていく。その一例が、土木工事などの現場で大量の土砂や岩石を運搬するダンプトラックだ。1974(昭和49)年、コマツ(株式会社小松製作所)は当時としては国内最大となる68tの積載量を誇る「HD680」を発表、さらに同年、1972年に発売された「HD320」の改良版も試作。小さいエンジンで高出力が得られる専用のガスタービンを独自開発・搭載した。
 コマツの「HD320」(画像提供:コマツ)
コマツの「HD320」(画像提供:コマツ)
また、アスファルト合材を生産・供給するアスファルトプラントも大型化と能率向上のための自動化が進められ、高速道路や空港の滑走路など大量のアスファルトを必要とする現場の需要に応えた。1972年には、当時国内最大級となった日工株式会社の「NAP-4000」が登場する。1960年代後半に使用されていた機種の生産能力が時間あたり10〜120tだったのに対し、同機は240tと圧倒的な性能を実現した。
なお、列島改造計画は地価高騰や物価上昇の要因となったことと、後述するオイル・ショックの影響などから早々に凍結された。しかし、その考え方は長期的な視点で見ても合理性に富み、現在に至る国土開発に大きな影響を及ぼしたことは間違いない。今から50年前に、第2東海道新幹線としてリニアモーターカーに言及しているのも興味深いところである。
オイル・ショック発生。省エネや公害対策が建機開発の新たなテーマに
1973年、長く続いた高度成長期が終焉を告げるときがやってきた。日本経済に引導を渡したのは、第4次中東戦争に端を発する第1次オイル・ショックである。石油輸出国機構(OPEC)によって原油の供給制限と輸出価格の大幅な引き上げが行われると、世界経済は大混乱に陥った。
エネルギーの8割近くを輸入原油に頼っていた日本ももちろん例外ではなかった。そして、1974年、日本経済は戦後初めてのマイナス成長に転じる。景気は低迷し、建設需要も落ち込んで、元の水準まで持ち直すのに5年ほどの時間を要した。
建機業界も当然のごとく需要が冷え込んだが、1970年代後半は建機開発が新たなイノベーションへと向かう入口でもあった。そのキーワードが「省エネルギー」である。オイル・ショックを経験し、産業界のみならず国民一人ひとりの省エネ・省資源の意識が高まる中、大きなエネルギーを消費する建機にも大幅な省エネやコスト減が求められるようになったのである。
同時に、高度成長のひずみのひとつである「公害問題」も日本国内で深刻度を増していた。建設現場においても排気ガスによる大気汚染をはじめ、水質汚染・騒音・振動など解決すべき多くの問題が挙げられた。
こうした課題を受け、メーカー各社では「エンジンなどの動力系や作業機構の省エネ化・効率化」「複合機化およびアタッチメント増加による多機能化」「大型建機から小型建機へのシフト」「環境に配慮した低騒音化」など、多彩な取り組みが進められた。
同時期に製造業の分野では産業ロボットの導入が進んでおり、建機の世界でも建機ロボットなどによる生産性の向上や省力化を目指した取り組みが始まっていた。
さらに、コンピューター制御や、機械工学と電子工学を融合させたメカトロニクスの技術の研究も進んでおり、これらの新しい技術も、省エネ・効率化・多機能化などの大きな力になろうとしていた。1978(昭和53)年ごろにはコンピューター制御の機械が登場しており、ダム工事の現場で生コンクリートを運搬するコンクリートトランスファーカーの自動運転なども始まった。
クローラテレスコ「YS450L」など工事の効率化に貢献する機種が登場
省エネ化、効率化などの流れの中で注目されるようになったのが、小型で小回りの利く建機であった。そのひとつが、1979(昭和54)年、油谷重工(現・コベルコ建機)から発売されたクローラテレスコ「YS450L」だ。
クローラテレスコとは小型のクローラクレーンのことで、油圧ショベルのアタッチメントに伸縮ブームを装着した移動式のクレーン。「YS450L」は同名の油圧ショベル「YS450L」をベースに開発され、バケット容量は0.45㎥、2.9tという吊り上げ能力を誇った。
 油谷重工の「YS450L」(画像提供:コベルコ建機)
油谷重工の「YS450L」(画像提供:コベルコ建機)
以前は不整地・軟弱地など足場の悪いところでの作業には油圧ショベルを利用したり、鉄板を敷いてトラッククレーンやラフテレーンクレーンを使用したりしていたが、クローラテレスコの登場により安定した吊り作業ができるようになった。条件付きだが、荷を吊ったまま走行できることも利点であった。
同じく小回りの利く建機としては、1981(昭和56)年にコマツが発売したミニホイールローダー「WA30-1」も挙げられる。バケット容量0.34㎥のアーティキュレートタイプで、少ない燃料で効率的な作業を行うことが可能。コンパクトな設計ながら、大型ダンプへの積み込みも容易で、建設はもちろんガス、水道、畜産、造園など幅広い分野で活用された。1984(昭和59)年より本格的に導入された同社のWAシリーズの先駆けとなった。
 コマツの「WA30-1」(画像提供:コマツ)
コマツの「WA30-1」(画像提供:コマツ)
また、現在、小型建機のグローバル・カンパニーとなっている株式会社クボタが油圧ショベルなどの大型建機から撤退し、小型建機へとシフトしたのが、まさにこの時期であった。
同社は都市化に伴う小規模工事が増加していることなどに着目し、1974年、全旋回式小型油圧ショベル「KH1」を開発。1979年には小型建機専門工場を新設し、「KH5H」、「KH90」などのミニバックホーを発売した。ミニバックホーのシリーズは、狭小地でも作業可能な超ミニタイプ、夜間工事にも対応した超低騒音設計タイプなどにも展開されていった。
安定したパワーと環境対策を実現した油圧ドリル「HCR200」
1970〜1980年代は新幹線や高速道路の建設が盛んに進められたが、それらの造成につきものといえるのがトンネル工事だ。トンネル掘削の代表的な方法のひとつが岩盤などを爆破する発破工法で、火薬を仕込むために穿孔(せんこう)するのが油圧ドリルの役割である。
日本で最初のロックドリルは、1914(大正3)年、古河鉱業足尾銅山機械工場(現・古河機械金属)が自山の手掘り作業を機械化すべく製造した「足尾式小型さく岩機」だといわれている。
その長い歴史の中で培ってきた経験を踏まえ、1977(昭和52)年、国産初の油圧式クローラドリルとして発売したのが、古河鉱業(現・古河機械金属)の「HCR200」であった。油圧式はバネなどは用いずに、ガスを併用しながら油圧を打撃エネルギーに変換。安定した穿孔性能を発揮し、「HCR200」においてはランニングコストの大幅削減、低騒音化、粉塵対策なども実現された。
 古河鉱業の「HCR200」(画像提供:古河ロックドリル)
古河鉱業の「HCR200」(画像提供:古河ロックドリル)
日本の建機技術が海外へ。アメリカや旧ソ連に輸出されたブルドーザー「D355」シリーズ
連載第4回で触れた通り、1970年代半ばに土木工事の主役を油圧ショベルに譲ったブルドーザーだが、コマツが開発した大型ブルドーザー「D355」のシリーズは、この時期から海外に活躍の場を広げていた。
ひとつは1970年に開発された「D355A-1」である。当時、圧倒的な支持を集めていた米キャタピラー社の「D9」より大きな馬力と力強いデザインが魅力の機種として、米国市場に食い込んだ。
さらに1975(昭和50)年、コマツは旧ソ連の依頼を受け、ブルドーザーの横にクレーンをつけたパイプレイヤーという仕様で「D155C-1」「D355C-3」を開発し、数千台を輸出している。ブルドーザーに92t吊りのクレーンを装着した「D355C-3」は、シベリアのパイプライン工事の現場では数台がひとつのチームとなって、溶接された鋼管を吊り上げ、埋設していったという。
 コマツの「D355C-3」(画像提供:コマツ)
コマツの「D355C-3」(画像提供:コマツ)
ダンプトラック「HD1200」は、旧ソ連の極寒地で活躍
同じくコマツが1978年に開発した120t積みのダンプトラックも旧ソ連で活躍した。新幹線のモーター技術を採用して開発された「HD1200」である。ダンプトラックの駆動には機械式と電気式があり、それまでは100t以上の大型機を電気式で動かすことのできるメーカーはなかったが、それをコマツが初めて実現した。
そして、この「HD1200」が活躍したのが旧ソ連の鉱山であった。マイナス60℃の極寒地であり、金属・非金属・油脂などあらゆる材質が予測のできない変化を起こした。コマツはトラブル対応のために現地に多くの駐在員を派遣、昼夜を問わずその解決に取り組んだという。
1980年代には、日本の油圧ショベルメーカーの技術を韓国のメーカーが導入し、安価な機種を開発して世界の市場に参入した。
戦前より欧米の技術に学びながら発展してきた日本の建機が、海外で活躍したり、技術が採り入れられるようになったとは感慨深いことといえるだろう。
積極的な全国展開で実績を伸ばしたアクティオの前身・新電気
1967年1月に設立された、アクティオの前身である新電気株式会社は、「列島改造ブーム」が起こる前年の1972年に、東京都江戸川区に新本社社屋と整備工場を開設した。
ベルトコンベアを導入した整備工場では、修理のみならず、機械テストや性能試験もライン上に取り込み、作業効率と修理品質の大幅な引き上げを実現した。さらに拠点間を結ぶオンラインネットワークを構築し、設備の稼働状況、資材、商品、経理などの情報をコンピューターで一元管理することで、多様化する顧客ニーズを迅速かつ正確に把握し、レンタル商品の稼働率の向上を図ることができた。
1973年、第1次オイル・ショックによって世の中の建設需要が縮小すると、同社も少なからず影響を受けた。しかし、社長(当時)の小沼光雄は萎縮せず、「これからの建設投資は地方に分散していくはずだ」との考えの下、積極的な全国展開を開始した。
 1978年、コーポレートカラーとして初めて赤を採用した
1978年、コーポレートカラーとして初めて赤を採用した
小沼の予想は当たり、全国各地の高速道路や新幹線建設の現場で、建機レンタルの需要は着々と増えていく。それとともに、「建機をレンタルすること」が世の中で一般的になっていったのである。
1970年に約2億円だった売上高は、10年後の1980(昭和55)年には約66億円となり、この年に本社を東京都中央区日本橋蛎殻町に移転した。そして、小沼が地方の次に見据えていたのは、シンガポール、マレーシアという経済の急成長が見込まれる東南アジアの国々であった。
取材協力(敬称略):一般社団法人日本建設機械工業会、コベルコ建機株式会社、株式会社小松製作所、古河ロックドリル株式会社
主要参考資料:「日本建設機械工業会30年のあゆみ」(一般社団法人日本建設機械工業会、2020年)、「写真で読み解く 世界の建設機械史 蒸気機関誕生から200年」(大川 總、三樹書房、2021年)
※記事の情報は2024年9月20日時点のものです。






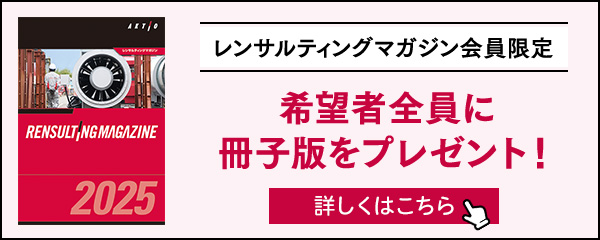













![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

