2022.03.16
【蟹澤教授の豊洲だより③】若手や女性の活力を引き出せる業界に 担い手不足や現場の高齢化、労働環境など、多くの課題を抱える建設業界。芝浦工業大学建築学部建築学科で教鞭を執る蟹澤宏剛教授は、アカデミックな立場で業界の課題に取り組み、日々、学生と向き合っていらっしゃいます。本連載では、豊洲キャンパスに研究室を構える蟹澤教授が、ご自身の研究や学生たちとの交流などを通して感じていることについて綴っていただきます。最終回となる今回は、業界の未来を担う若手や女性の活躍についてです。
文:蟹澤 宏剛(芝浦工業大学建築学部建築学科教授)
構成:奥野 慶四郎(ライター)
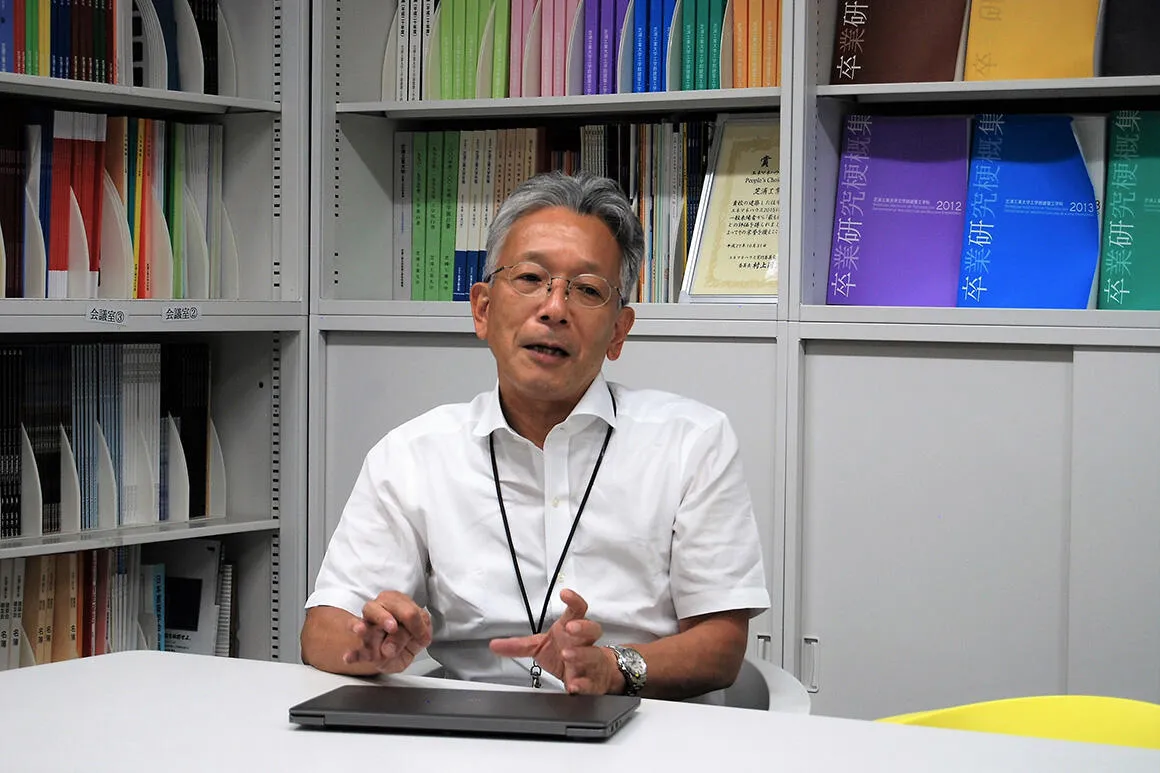
活力ある若手は建設業界の「宝」
私の研究室で学ぶ学生たちは、もともと建築が好きで、その多くは卒業後、建築に関わる仕事に就きます。
私が担うのは、彼ら彼女らがプロとしてやっていくための土台作りで、必要な知識や実務の基本を教えること。しかし、それだけでなく、仕事の醍醐味やものづくりの素晴らしさを伝え、彼ら彼女らのモチベーションを高めてあげることも大切な役目だと心得ています。学生たちを気持ちよく送り出してあげたいですし、活力ある若手は建設業界にとって「宝」ですから。
実は「内向き志向」ではない学生たち
内向き志向が強く、野外などでの現場仕事より室内での事務仕事の方を好む――。メディア発の話題や世論から、今の学生にはそんな大人しいイメージを抱きがちですが、実はそうではありません。
例えば、ボランティア活動。災害被災地域への支援に参加する学生は大勢います。建築系の学生を対象にした「途上国で学校を造る」といった公募型のプロジェクトもすぐに定員に達すると聞きます。こうした活動は設計などではなく、清掃や廃棄物の処理、レンガを積むといった肉体労働や汚れ作業が多く、いわゆる「3K」に近い内容ですが、それでも学生たちは自主的に取り組んでいます。
私の研究室の学生たちも、古民家再生の活動などがあれば喜んで出かけていきます。「現場で懸命に汗をかいて、人や社会に貢献したい」。そんな思いを持つ学生がたくさんいることの証左でしょう。
巨匠作品のディテールを凝視して学ぶ
大学の新入生に、「素晴らしいと思う建築家」についてのレポートを書かせることがあります。提出されたレポートのうち、半分くらいは今人気のある日本の有名建築家を取り上げています。その中身も、本人の考えというより、誰かが書いた論評などを参考にしたものが多い。
新入生だから仕方がありませんが、在学中に「よい建築とはどこがすごいのか」を学び、卒業する頃には、それを自分で見極められるようになっていてほしいと思います。「目利き」になるためのトレーニングとして、学生には巨匠が設計した建築物のディテールを「凝視」することを勧めています。私の言う巨匠とは、日本なら前川國男や丹下健三、海外ならノーマン・フォスター、ル・コルビュジエなどですが、彼らの作品はディテールが違う。細部にもかかわらず、構造力学や美観、材料など、あらゆる要素を計算し尽くして設計・施工されているのです。
よい建築物と並の建築物とではディテールに差がありますから、講義では学生たちに「近くから張り付いて見ろ」「床の下はしゃがみ込み、カメラを差し込んで見ろ」と指導しています。
職人をリスペクトする気持ち
他方、設計を匠の技で形にしてくれる職人たちを常に尊敬する心を持ってほしいと思います。例えばゼネコンに入って現場の技術者になると、職歴何十年のベテランの職長よりも、いきなり立場が上になってしまうこともありますが、謙虚な姿勢で接することが大切です。職人たちとは一緒にものづくりをする対等な立場であることを肝に銘じるとともに、「自分たちにはできないことができる」ということに敬意を払いなさいと伝えています。
私の研究室では毎年、新潟県の佐渡島(さどがしま)で建築の実務を学ぶ合宿を行っています。実費だけをいただき、公民館のリニューアルや酒蔵の試飲室の家具・内装のリフォームなどを、研究室の学生が主体となって行うのです。
施工については、地元の棟梁が指導してくれるのですが、学生たちにとって「神業(かみわざ)」とも言える棟梁の職人技を目の当たりにすると、学生たちは「すごい!」と圧倒される。職人をリスペクトする気持ちが自然に芽生えるわけです。そのような経験を積ませていることもあって、私の研究室の学生は、現場の職人とすぐに信頼関係を築くことができます。
 佐渡島での合宿の様子。研究室の学生や地元の棟梁と一緒に作業をして汗を流す
佐渡島での合宿の様子。研究室の学生や地元の棟梁と一緒に作業をして汗を流す
女性が生涯働ける職場環境を
現場の担い手不足が深刻化し、建設業界が女性技術者に寄せる期待はますます大きくなっています。私は、ふだん学生たちと接している中で、女性は現場の仕事に向いていると思っています。まず、一般的にコミュニケーション力が高いことがあげられると思います。そして、個人差はもちろんありますが、学生たちを見ていると、実は体も男性に負けてはいないと思います。さすがに「筋力」は平均的には男性の方が強いかもしれませんが、現場実習などで女子学生たちを見た印象からは、総合的な「体力」といったものは男性と同等以上ではないかと実感します。特に、暑さや寒さには女性の方が強い面があるのではないでしょうか。
ただ、彼女たちのポテンシャルを十分に引き出し、存分に活躍してもらうためには、業界全体で労働環境を改善する必要がありそうです。大手の建設会社は、10年ほど前から総合職の採用枠で本格的に女性の採用を始めました。彼女たちに生涯にわたって活躍してもらうためには、「産休や育休を取りやすくする」「勤務地の近くに保育所を設ける」といった産前産後・子育てへのサポートも欠かせません。
この業界で働く一人ひとりが、女性の活躍に対する意識を変えていければ、女性たちはより生き生きと働けるようになり、それは業界全体にとっても大変意義のあることだと考えます。
※記事の情報は2022年3月16日時点のものです。

- 蟹澤宏剛(かにさわ・ひろたけ)
芝浦工業大学建築学部建築学科教授。1967年生まれ。千葉大学大学院(自然科学研究科博士課程)を修了後、財団法人国際技能振興財団に就職。その後、工学院大学や法政大学、ものつくり大学などで講師を務めた後、2005年から芝浦工業大学工学部建築工学科助教授、09年から現職。国土交通省の担い手確保・育成検討会委員、社会保険未加入対策推進協議会会長、建設産業戦略的広報推進協議会顧問、建設産業活性化会議委員などを歴任。技能者の社会保険未加入問題を顕在化させた。
(※芝浦工業大学は、2017年に工学部建築学科、建築工学科およびデザイン工学部デザイン工学科建築・空間デザイン領域を統合・再編し、建築学部建築学科を開設した)






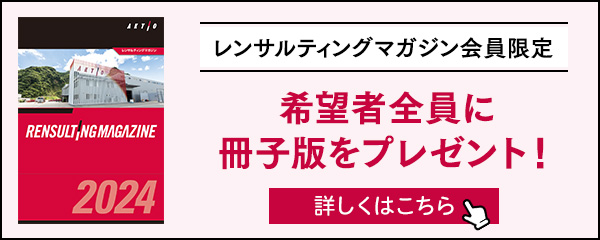













![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

