2021.09.22
建設現場の働き方が変わる【建設業の未来インタビュー③ 後編】 建設業界が直面する担い手不足や現場の高齢化、労働環境などの問題。芝浦工業大学建築学部建築学科の蟹澤宏剛教授は、解決の切り札の1つとして建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用を挙げる。CCUSをベースとして、社会保険加入の促進や、技能者の教育システムの構築などを提唱する。聞き手は建設系メディアなどでフリーライターとして活躍中の三上美絵氏。
ゲスト:蟹澤 宏剛(芝浦工業大学建築学部建築学科教授)
聞き手:三上 美絵(フリーライター)

業界改革の切り札「CCUS」
――働き方改革の推進に向けて、2019年に「建設キャリアアップシステム」の本格運用が始まりました。どのような仕組みですか。
蟹澤 建設業界内ではCCUS(Construction Careerup System)と呼ばれています。技能者一人ひとりについての本人情報、所有資格や社会保険の加入状況、現場の就業履歴などを、業界統一のルールで登録・蓄積。その人がどこの誰で、建設現場で働いていることをしっかりと証明する仕組みです。
まず登録時に技能者は住所や氏名といった本人情報、社会保険の加入状況などを登録し、クラウドに情報が登録されたICカードを受け取ります。勤務する現場の入退場の際にカードを読み取ってもらい、その技能者が、「いつ、どの現場で、どのような作業に従事したか」といった就業履歴をシステムに蓄積。登録した技能者のデータベースを構築するわけです。
登録した技能者は、記録された保有資格や就業履歴を基に、自分の技能レベルを4段階で評価してもらう制度を利用することもできます。カードは技能レベルによって色分けされていて、レベルが上がると、色が白→青→シルバー→ゴールドと変わっていきます。日頃からスキルの向上や資格取得に努める技能者が適正に評価され、待遇が改善されていく。そんな効果が期待できます(図A)
●図A 「CCUS」(建設キャリアアップシステム)とは
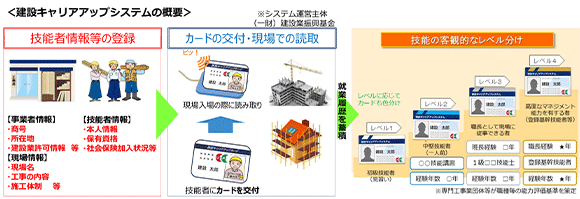
出典:国土交通省「建設キャリアアップシステムの構築」から、概要説明図の部分を切り出して掲載。建設キャリアアップシステムについては国土交通省の「建設キャリアアップシステム」に詳しい説明と関連資料が集められているのでご参照いただきたい。
※CCUS(建設キャリアアップシステム)のシステム運営は一般財団法人建設業振興基金が担当している。
――技能者の方々が、それぞれのスキルや経験に応じた評価や処遇を受けられる環境を整えるための制度ですね。
そうです。例えば欧米では、ギルド(欧州)やユニオン(米国)といった、技能者の能力を評価したり育成したりする仕組みがあるのですが、日本にはありませんでした。個々の技能者の経歴を証明するような制度がなかったので、極端な話、熟練のすご腕職人も、自分で「〇〇工です」などと言っている「自称職人」も一緒くたでした。
しかし、CCUSの運用開始によって、「何年働いてきたのか」「どこの現場にどれだけ入って、どんな仕事をしていたのか」「現場で事故を起こしたことがないか」「どんな資格を持っているか」など、個々の技能者の経歴や能力を客観的に証明することができるようになった。これをベースにしていけば、頑張ってきた人がきちんと評価される業界になるのではないかと期待しています。

――CCUSの登録状況や、その活用方法について教えてください。
蟹澤 まず登録者数ですが、2021年6月時点で60万人程度です(図B)。この数字から見れば、大手ゼネコンの1次下請けクラスの企業が雇用する技能者は、ほぼ登録されたとみなせるでしょう。今後は、2次下請けクラスの企業や地方の中小企業などで雇われている技能者の登録を促していくことになりますが、業界では、登録者数の最終目標を150万~200万人に置いています。
具体的な活用方法で、最も有効と考えられるのは現場の入場管理。例えば公共工事では、いずれCCUSの登録者しか入れないような体制になるでしょう。国土交通省は2023年の体制構築を目標にしていて、大手ゼネコンも基本的にはそれに追随していく構えです。いま、すでに入退場システムを導入している現場は多いですから、システム上にCCUS登録の条件などを加えるなど、段階を踏んで制限していき、将来的にはCCUS未登録者は現場に入場できなくなるでしょう。
●図B 「CCUS」への技能者登録数の推移
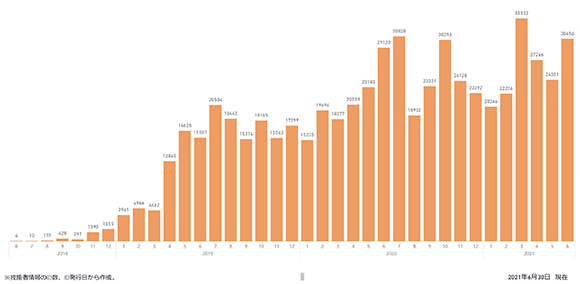
出典:一般財団法人建設業振興基金「建設キャリアアップシステムの運営状況について(2021年7月)」(https://www.ccus.jp/attachments/show/60e6c91b-f32c-4c62-ac84-7bcf6fabc59e
)からグラフを抜粋。2021年6月末時点の技能者登録数は累計601,373人。
――先生の活動やCCUS登録者の増加などによって、社会保険の加入状況は改善されつつありますか。
蟹澤 国土交通省が社会保険の未加入問題に本腰を入れ始めたのが10年ほど前。当時、私も業界団体などが主催する講演会に呼ばれ、この問題について話をすることがありましたが、聞いていた企業の方々の抵抗が強く、「職人が社会保険に入るなんて無理だ」「あなたは現場を知らない」などと、抗議を受けたものです。
しかし、数年前から社会保険の問題に対する業界の意識が変わってきたと感じます。地方では、以前と変わらぬ状況が続いているところもあるようですが、少なくとも、大手ゼネコンや中小ゼネコンが組織する団体の人から「技能者の社会保険加入は無理だ」といった言葉を聞くことはなくなりました。企業のトップが「この問題に本気で向き合わなければ担い手が足りなくなる」という危機意識を持つようになってきているからでしょう。国土交通省の調査を見ても、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3保険の加入状況は、10年前と比べると改善されていることが分かります(図C)。
●図C 社会保険加入状況の推移/企業の3保険加入割合(元請・下請次数別)
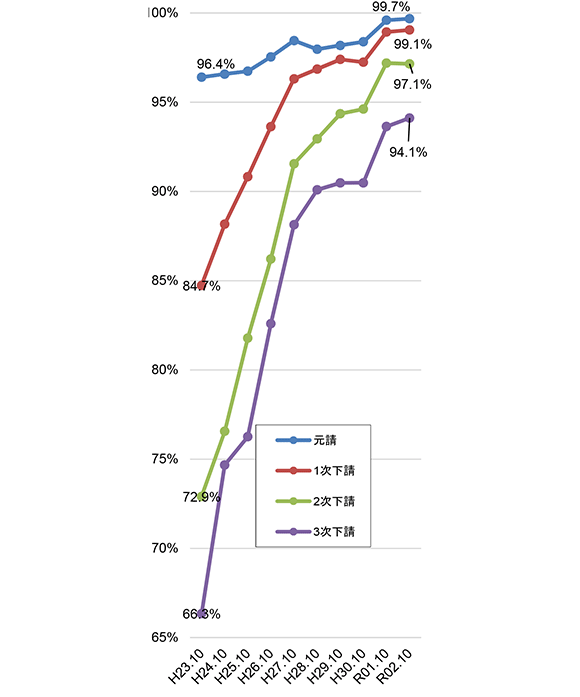
出典:国土交通省「社会保険加入対策及び最新状況」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001393090.pdf)のP.17「社会保険加入状況の推移(地方別、元請・下請次数別)」からグラフを抜粋した。
※公共事業労務費調査(平成23年~令和2年)における3保険加入状況。全体的に加入割合は上昇傾向にある。ただし、元請企業と比較して高次の下請企業は加入割合が低い傾向にある。
――働き方を改善していくための方策としては、CCUSのほかにICT活用による生産性向上も有効だと思います。どんな期待を寄せますか。
蟹澤 作業の効率化や省力化を実現するICTは、働き方改革をサポートするツールとして必須でしょう。土木の現場ではドローンやレーザースキャナーによる3次元測量。さらに、そこで収集した3次元データを活用したICT建機の操作支援や自動制御などが先行しています。
一方、建築の現場では、自動搬送ロボットや溶接ロボットなどの導入が進むほか、BIM(Building Information Modeling)の3次元モデルをベースに、実際の建築現場の環境とそっくり同じものを仮想空間内に再現する「デジタルツイン」と呼ばれる技術も利用され始めています。仮想の現場でのシミュレーションによって効率的な施工手順を導き出したり、実際の現場と仮想の現場とを突き合わせることによって設計との誤差を「見える化」して調整したりするなど、今後、多面的な展開が期待されます。
土木でも建築でもICTの導入によって、熟練オペレーターでなくても正確な重機操作が可能になる、現場の関係者全員が現場に関する最新情報をリアルタイムに共有できる――といった具合に、施工実務や施工管理の効率化や省人化、さらには施工精度の向上にも大きな効果をもたらし始めています。今後は、働き方改革の推進になくてはならないツールになるでしょうね。
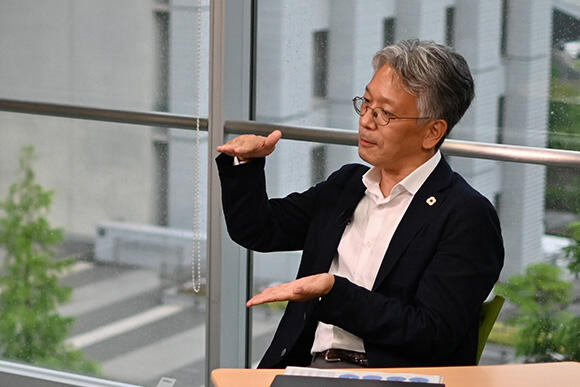
技能者の処遇改善と教育システム構築を目指す
――業界の発展に向けて、今後はどのようなテーマに取り組まれますか。
蟹澤 再優先課題は、いわゆる「偽装一人親方問題」ですね。一人親方というのは、個人・請負で働く技能者のことですが、勤務時間に制限がないので「休まずに働いてたくさん稼ぐ」といった働き方をする人がいます。一方で、特定の企業とだけ、専属下請けというような形でしか働かないという人もいます。
問題なのは後者の場合で、その企業は、技能者が一人親方で保険料などを支払わずに済むのをいいことに、請負扱いで安く使い続けていることになります。こういう場合、その技能者を社員にすべきというのが私の考え方。業界と一緒に改善を図っていきたいと思っています。
逆に、前者のようなタイプで腕のいい技能者たちは、対価の面、賃金の面で高く評価されるようになっていけば、「フリーランス・プロ職人」といった感じのとても魅力的な働き方ができると思います。例えば、休みも自分で決められる。外国の技能者には、年に1回、1カ月くらい休む人も多くいます。たくさん稼いでたくさん休むとか、朝早く出て夕方には家に帰って子どもと遊ぶとか、そういう働き方も、能力があって裁量が大きくなればこそ。これは、外で働く建設業の魅力になると思いますね。
――技能者の教育システムの構築も重要なテーマとなりそうですね。
蟹澤 海外には「見習い制度」という技能者を業界共通で育てる仕組みがあります。建設業の技能や技術は会社によって違うものではなく業界共通のものです。また、専門工事会社などは会社の規模が小さいので、それぞれが個別に人材育成するというのはすごく大変なので、こうした仕組みを作っているのですが、同様の仕組みが日本にも必要です。

例えば、業界共通で3年間は同一賃金で働く。その代わり、週末は学校で仕事に必要な知識を学べる。彼らを教育するにはお金も必要になるので、ここはCCUSを活用して、カードを1回タッチするたびに、その技能者を使っている会社が少しずつお金を積み立てていくといった形で基金も構築する。働く方も、人を使う方も、良い関係ができるのではないでしょうか。
【取材を終えて】
建設業の現場が抱えている課題や解決に向けた方策、などがよく分かりました。蟹澤先生のような学識経験者を含め、産学官の尽力によって業界内の雰囲気や取り組み姿勢も変わってきたように感じます。建設業は世界的に見ても、非常に古くからある重要な産業の1つです。それだけに、業界の活性化は社会的意義も大きなものがあると思います。話題に出たCCUSやICTによって、業界の魅力がさらに高まることを期待したいと思います。
※記事の情報は2021年9月22日時点のものです。

- 蟹澤宏剛(かにさわ・ひろたけ)
芝浦工業大学建築学部建築学科教授。1967年生まれ。千葉大学大学院(自然科学研究科博士課程)を修了後、財団法人国際技能振興財団に就職。その後、工学院大学や法政大学、ものつくり大学などで講師を務めた後、2005年から芝浦工業大学工学部建築工学科助教授、09年から現職。国土交通省の担い手確保・育成検討会委員、社会保険未加入対策推進協議会会長、建設産業戦略的広報推進協議会顧問、建設産業活性化会議委員などを歴任。技能者の社会保険未加入問題を顕在化させた。
(※芝浦工業大学は、2017年に工学部建築学科、建築工学科およびデザイン工学部デザイン工学科建築・空間デザイン領域を統合・再編し、建築学部建築学科を開設した) -

- 三上美絵(みかみ・みえ)
土木ライター。1985年に大成建設に入社。1997年にフリーライターとなり、「日経コンストラクション」などの建設系雑誌や「しんこうWeb」、「アクティオノート」などのWebマガジンなどに連載記事を執筆。一般社団法人日本経営協会が主催する広報セミナーで講師も務める。著書に「かわいい土木 見つけ旅」(技術評論社)、「土木技術者になるには」(ぺりかん社)、共著に「土木の広報」(日経BP)。土木学会土木広報戦略会議委員、土木広報大賞選考委員。
〈ご参考までに...〉
オリジナル動画「建設業の未来インタビュー【3】」後編をご視聴いただけます!






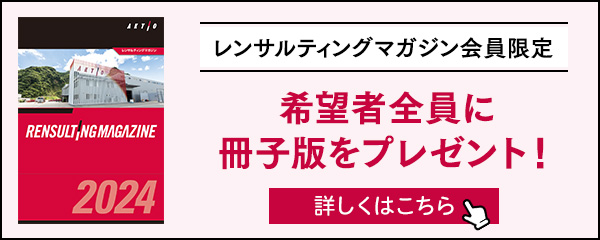













![自著を語る[自著で紹介する建設の魅力]](/common/images/side_bnr_books.jpg)
![どぼく偉人ファイル[古今東西のどぼく偉人をピックアップ]](/common/images/side_bnr_greatman.jpg)
![建機の歴史[建機にまつわる歴史を紹介]](/common/images/side_bnr_history.jpg)
![天気の読み方[建設現場で役立つ!]](/common/images/side_bnr_weather.jpg)

